お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
今回は、たまーに勘違いしている人がいる条文の読み方についてです。
ズバリ、令132条(2以上の全面道路がある場合)です。
いわゆる、「2Aかつ35m」の条文です。
2以上の全面道路がある場合、必ず2Aかつ35mを使わないといけません。
理由は、
です。
「みなしてよい」or「みなすことができる」とは書かれていません。
では、条文を用いて解説していきます。

令132条(2以上の全面道路がある場合)

第1項を見ていきます。
建築物の全面道路が2以上ある場合においては、幅員が最大な前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以上の区域及びその他の全面道路の中心線から水平距離が10mをこえる区域については、すべての全面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するとみなす。
解説
読みやすく書き換えると
建築物の全面道路が2以上ある場合は、
幅員が最大な前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以上の区域
と
その他の全面道路の中心線から水平距離が10mをこえる区域
は、
すべての全面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するとみなす。
となります。
つまり簡単にいうと、
2以上の道路がある場合、
黄色と緑の区域は、幅員が一番広い道路の幅員があるものとしてみなして道路斜線を検討してね
ってことです。
ここで、着目すべきは条文の語尾です。
なんと書いてありますか?
み・な・す
と書いてありますよね?
なので、必ず使わないといけないのです。
もし使っても使わなくてもいいのであれば、
条文は、「みなしてもよい。」or「みなすことができる。」という書き方をしなければいけません。
というわけで、2Aかつ35mは必ず使わないといけないのです。
さいごに
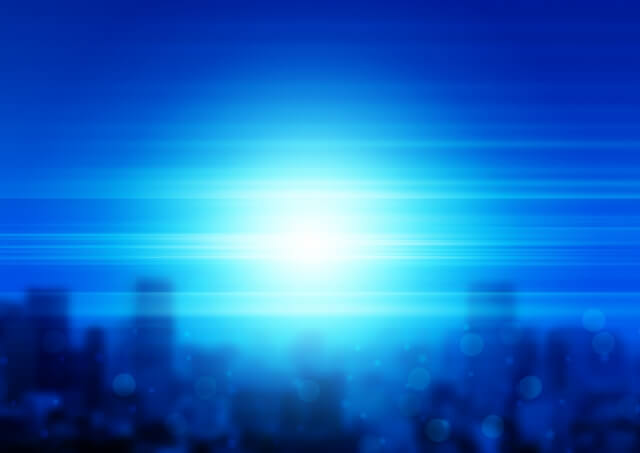
以上、【意外と間違える】2Aかつ35mは、必ず使わないといけない理由
についてでした。
結論は、
です。
条文は、正確な言葉を選びつくられています。
本当にめちゃくちゃ頭のいい人がつくったんだなあと感じます。
法律をつくった人の気持ちを読み取るように条文は読んでいきたいものです。
ともかく、みなさんも条文を読むときは、一字一句正確に読むように心がけましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
追記
令132条(2以上の全面道路がある場合)の他に
・令134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
・令135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
・令135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
・令135条の4(北側の全面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
などの条文にも「みなす」という表現が出てくるのでご注意下さいね。
