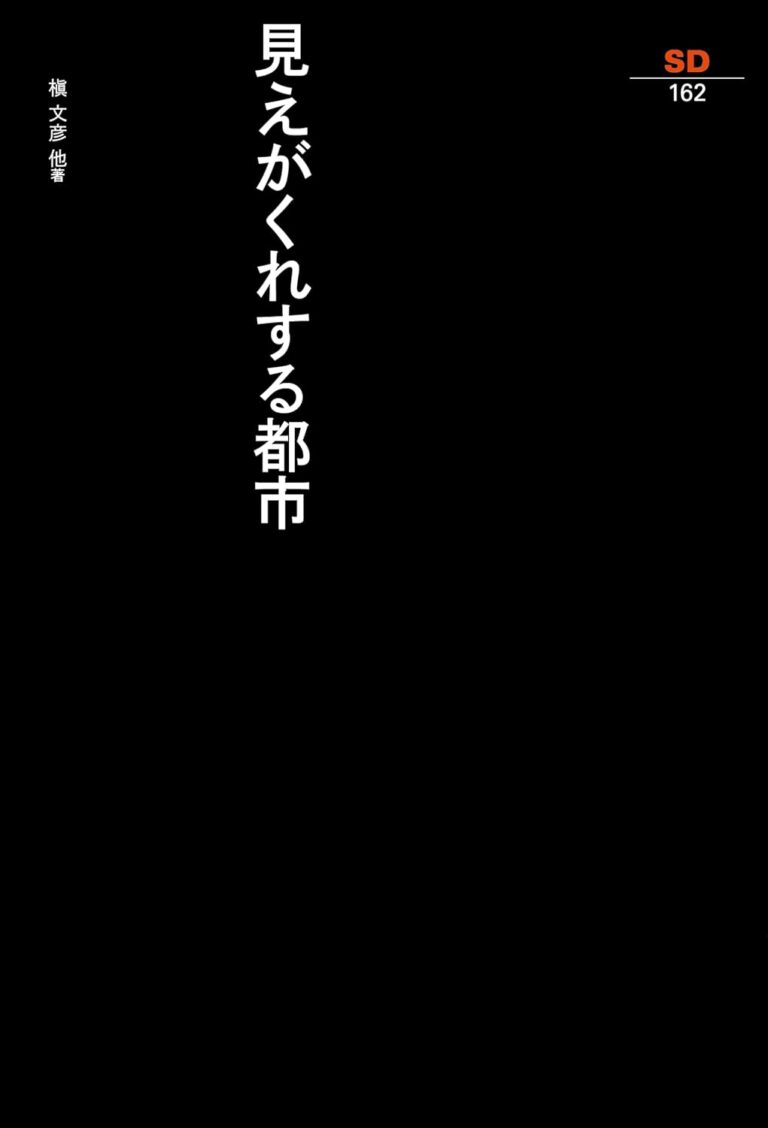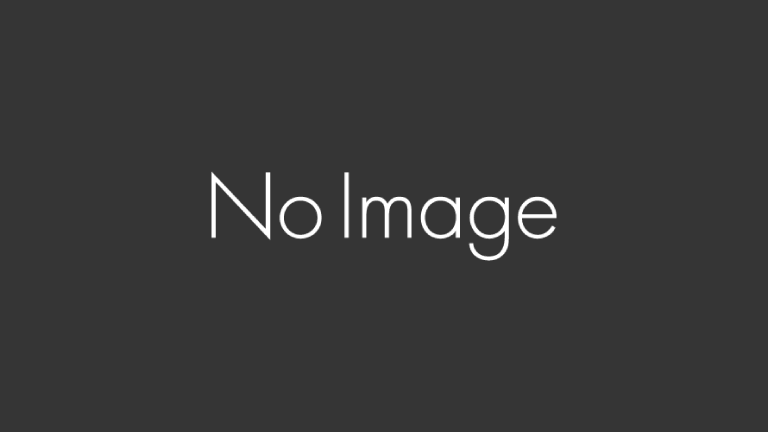概要
江戸から東京へと劇的な変化を遂げた都市の姿を、「見えがくれ」という独特な視点から読み解いた都市論です。
都市は、まるでミルフィーユのように、様々な歴史的な層が積み重なってできています。
過去の都市の面影が、現在の都市の中にひっそりと「見えがくれ」している。
そして、都市は生き物のように常に変化し続けており、その過程で、あるものは人々の目に触れる場所に現れ、またあるものは記憶の彼方へと消えていきます。
さらに、都市は人々の記憶や物語によって意味を与えられた、まるで記号の集合体のようです。
しかし、その記号もまた、時代とともに変化していくのです。
これらの視点を通して、江戸から東京への都市の変化を、単に外観が変わったというだけでなく、そこに暮らす人々の生活や文化、記憶の変化として捉えようとしているのが、この本の面白いところです。
具体的な事例としては、江戸城が皇居へと姿を変えたこと、武家地が消え、新しい市街地が形成されたこと、そして鉄道の敷設によって都市構造が大きく変化したことなどが挙げられます。
これらの事例を通して、都市の「見えがくれ」を読み解くことで、都市の歴史や文化に対する理解がぐっと深まるはずです。
都市に興味がある人はもちろん、都市計画や都市デザインを学ぶ人、そして日本の歴史や文化に興味がある人にも、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
間接引用
| 章のタイトル | 都市は、時間の経過とともに、さまざまな変化を経験する。その変化は、古いものが完全に消え去るのではなく、新しいものと混ざり合い、重なり合いながら、都市の風景を形成していく。
都市の記憶は、人々の心の中に蓄積され、世代を超えて受け継がれていく。都市の風景は、その記憶を映し出す鏡であり、人々のアイデンティティを形成する。 |
| 序章 見えがくれする都市 | 江戸から東京への変貌は、単なる都市の外観の変化ではなく、社会、文化、人々の意識の変化を伴うものであった。
明治維新は、都市の構造を大きく変え、近代的な都市の基礎を築いた。しかし、その過程で、江戸時代の文化や記憶が失われていった。 |
| 第一章 江戸から東京へ―都市の変貌 | 都市は、歴史的な層が積み重なってできており、過去の都市の姿が現在の都市の中に残っている。それは、まるで地層のように、都市の記憶が堆積している状態である。
都市の重層性は、都市のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たす。過去の記憶は、現在の都市を理解するための手がかりとなり、未来の都市を創造するための礎となる。 |
| 第二章 都市の重層―記憶の堆積 | 都市は、常に変化し続けており、その変化の過程で、あるものは現れ、あるものは消えていく。それは、都市のダイナミズムであり、都市の生命力である。
都市の変化は、人々の生活や文化に大きな影響を与える。新しい技術や文化が導入されることで、都市の風景は一変し、人々の価値観も変化する。 |
| 第三章 都市の動態―変化のダイナミズム | 都市は、人々の記憶や物語によって意味を与えられた記号の集合体である。都市の風景は、記号のネットワークであり、人々のコミュニケーションを支える。
都市の記号は、時代とともに変化する。新しい記号が生まれる一方で、古い記号が消えていく。それは、都市の文化的な変化を反映している。 |
| 第四章 都市の記号―意味の生成 | 都市は、人々の記憶や物語によって意味を与えられた記号の集合体である。都市の風景は、記号のネットワークであり、人々のコミュニケーションを支える。
都市の記号は、時代とともに変化する。新しい記号が生まれる一方で、古い記号が消えていく。それは、都市の文化的な変化を反映している。 |
| 都市の未来は、過去の記憶と現在の変化、そして未来への展望が織りなす物語である。都市は、常に変化し続ける存在であり、その変化は、人々の創造性と想像力によって導かれる。
見えがくれする都市の未来は、過去の記憶を尊重し、現在の変化を受け入れ、未来への希望を抱くことによって開かれる。都市は、人々の夢と希望を叶える場所であり、常に進化し続ける存在である。 |
ひとこと

Amazon…