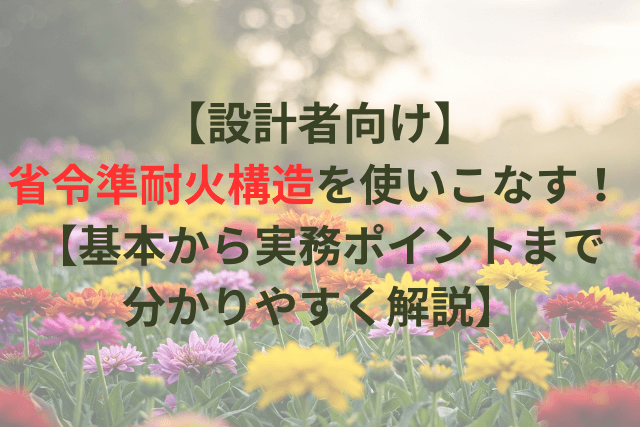省令準耐火 https://t.co/tdQ9GHbA9F
— いしいさん【建築基準法コンサルタント】 (@ishiisans) April 22, 2025
設計者の皆さん、こんにちは! 日々の設計業務、お疲れさまです。
特に木造住宅を手がける際、「省令準耐火構造」はコストメリットと性能の両立を図る上で、
よく検討される選択肢の一つですよね。
ただ、「あれ?これって法規上の扱いはどうだっけ?」
「施主さんへの説明、どうしたら分かりやすいかな?」など、
改めて確認したいポイントもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、「省令準耐火構造」について、
基本のキから実務上の注意点まで、
設計者の皆さんの視点で分かりやすく整理してみました。
日々の業務や施主さんへの提案に、ぜひ役立ててください!
1. まず押さえたい基本:「省令準耐火構造」ってどんなもの?
最初に、基本事項として、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 建築基準法に直接の定めはない、という点が重要!
- 意外と誤解されやすいのですが、建築基準法や関連法令の中に「省令準耐火構造」というズバリの定義はありません。
- 法に定められた「準耐火構造」とは別物です。
- 法第2条第七号の二で定められている「準耐火構造」(一定時間、火災に耐える性能)とは、明確に区別して考える必要があります。
- じゃあ、その正体は? → 主に住宅金融支援機構などが定める「仕様」です。
- 一般的に「省令準耐火構造」と呼ばれるものは、住宅金融支援機構(フラット35でお馴染みですね)などが、木造軸組工法などを対象に「準耐火構造に準ずる防火性能を持つ住宅の仕様」として定めているものを指すことが多いです。「省令」という名前ですが、法律そのものではなく、これらの仕様規定の呼称として広く使われています。
- 目的は「燃え広がりを抑えて、避難時間を稼ぐ」こと。
- 外からの延焼防止、部屋から部屋への燃え広がり防止、骨組みがすぐに燃えないようにする、といった工夫で、火災時の安全性を高めることを目指しています。
2. 仕様のポイント:どんな工夫がされているの?
具体的な仕様は、適用する基準(住宅金融支援機構の仕様書など)によって変わってきますが、設計や監理で特にチェックしたい主なポイントはこんな感じです。(詳細は必ず適用基準をご確認くださいね!)
- 外壁・軒裏:外部からのもらい火対策
- 防火構造(例:防火サイディング+下地+石膏ボード)などで、外からの火に強くします。
- 壁・天井(室内側):部屋から部屋へ燃え広がるのを遅らせる
- 強化石膏ボードなどを、仕様書通りにしっかり施工(厚さ、貼り方、留め付けなど)することが大切です。
- 間仕切り壁などは、小屋裏や天井裏までしっかり到達させます(ファイヤーストップも忘れずに!)。
- 床・階段・構造材:他への延焼を遅らせ、構造を守る
- 床や階段、柱・梁なども、石膏ボードなどでしっかりカバーします。
注意点: これらはあくまで「仕様」です。建築基準法が求める性能規定(例えば防火区画など)とは考え方が違うので、「省令準耐火だから、あの規定はクリア」とはならない点に注意しましょう。
3. 採用するメリット:施主にも嬉しいポイントは?
省令準耐火構造を採用すると、どんな良いことがあるのでしょうか?
- 【最大の魅力!】火災保険料がグッとお得に!
- これが施主さんにとって一番分かりやすいメリットかもしれません。多くの場合、一般的な木造(H構造)ではなく、鉄骨造などと同じ「T構造」扱いとなり、火災保険料がかなり安くなります。
- 保険契約時には、設計図書や適合証明書などでT構造であることを示す必要があります。
- フラット35の利用や金利優遇にも
- 住宅金融支援機構の技術基準に適合するので、フラット35が利用しやすくなります。金利優遇の対象になることも。
- 「火事に配慮した安全な家」として説明できる
- 法的な準耐火構造ではないものの、標準的な木造より安全性が高いことを、施主さんに具体的に伝えられます。
- コストと性能のバランスが良い選択肢に
- 準耐火構造にするよりコストを抑えつつ、防火性能を高めたい場合に有効な選択肢です。
4. 設計・監理で注意したいこと:押さえておくべきポイント
メリットがある一方で、設計・監理を進める上では、以下の点に注意が必要です。
- コストアップへの配慮
- 標準的な木造と比べると、材料費や手間が増えるため、建築コストは上がります。初期費用と、火災保険料などランニングコストの削減効果を合わせて、施主さんに分かりやすく説明できると良いですね。
- 「仕様」はきっちり守る!
- これは性能規定ではないので、決められた仕様(材料、寸法、施工方法)を守ることが大前提。自己判断での変更はNGです。断熱材の施工や配管貫通部の処理など、細かい部分も仕様通りか、しっかりチェックしましょう。
- プランニングへの影響も考慮
- 壁が少し厚くなったり、使える材料に制約が出たりすることもあるので、計画の早い段階から意識しておくとスムーズです。特に大きな吹き抜けなどは注意が必要なケースも。
- 施工品質が性能のキモ!
- 石膏ボードの留め付け方ひとつで性能が変わってきます。ファイヤーストップ材の施工なども含め、現場での丁寧な施工と、監理者による確実なチェックが非常に重要です。
- 法規上の制限と混同しないように!
- 防火地域・準防火地域で求められる「耐火建築物」「準耐火建築物」とは別物です。 省令準耐火構造にしたからといって、これらの法的要求をクリアできるわけではないので、建築地の法規制は必ず確認しましょう。
- 法22条区域の外壁防火措置についても、省令準耐火の仕様が結果的に満たすことが多いですが、別途確認は必要です。
- 関連書類の準備
- 確認申請で特別な手続きは少ないですが、フラット35の適合証明や火災保険用の書類など、必要なものを把握し、スムーズに準備できるようにしておきましょう。
5. まとめ:省令準耐火構造を上手に活用するために
省令準耐火構造、いかがでしたでしょうか? メリットや注意点をしっかり理解し、
プロジェクトの特性に合わせて上手に活用することで、施主満足度の向上にも繋がるはずです。
〇メリット(特に火災保険料!)と注意点をしっかり伝える
〇仕様の遵守と施工品質の確保を徹底する
これらのポイントを押さえて、施主さんにとってベストな提案をしていきたいですね。
特に施工品質が性能の鍵を握りますので、現場との連携を密に、より良い家づくりを目指していきましょう!