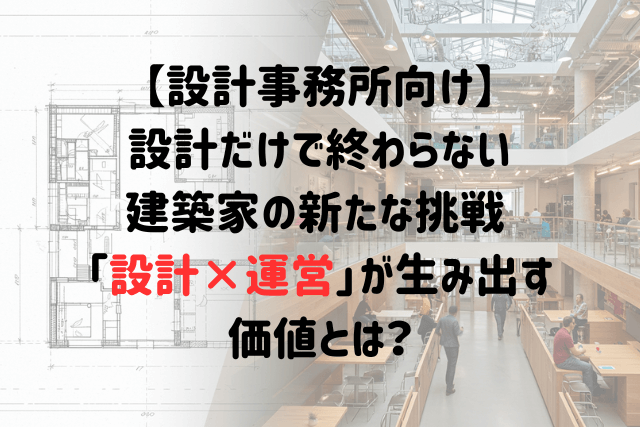多くの設計事務所では、設計、監理、そして引き渡しをもってプロジェクトの一区切りと考えるのが一般的かもしれません。
しかし、建物の「使われ方」にまで視野を広げ、積極的に関わっていく「設計×運営」という新しい働き方が、今、注目を集めています。
これは、設計事務所のビジネスのあり方や社会との関わり方に、変化をもたらす可能性を秘めています。
なぜ今、「設計×運営」が求められるのか?
- 建物の価値を長く保つために:
- どんなに良い設計でも、使われ方次第でその魅力が十分に活かされないこともあります。
- 運営に関わることで、設計の意図をしっかり伝え、空間のポテンシャルを長く引き出すことにつながります。
- 変化する社会のニーズに応えるために:
- 建物の使われ方や求められるものは、時代とともに変わっていきます。
- 運営を通じて利用者のリアルな声に耳を傾け、変化に柔軟に対応することで、建物が長く愛され、活用される可能性が高まります。
- 設計事務所の新たな収益の柱として:
- これまでの設計監理料だけでなく、運営に関するコンサルティングや業務の受託、あるいは自社で事業を行うなど、新しい収益のチャンスが生まれるかもしれません。
- より良い設計のためのヒントを得るために:
- 運営の現場で聞かれる利用者の声や課題(使い勝手、改善点など)は、非常に実践的で貴重な情報です。
- こうしたフィードバックを次の設計に活かすことで、より利用者の視点に立った、質の高い設計を目指せます。
「設計×運営」の具体的な関わり方
設計事務所が運営に関わるスタイルは様々です。
- 企画段階から一緒に考える:
- 事業の仕組みづくりや、どんなテナントを入れるかなど、ソフト面からプロジェクトに参加する。
- 運営の相談に乗る:
- 完成した後の施設の運営について、設計者の視点からアドバイスやサポートを行う。
- 運営する人たちと協力する:
- 運営会社としっかり連携を取り、設計の意図を共有したり、改善提案を行ったりする。
- 運営の一部を担う:
- イベントの企画・実施、情報発信、コミュニティづくりのお手伝いなど、特定の運営業務を受け持つ。
- 自分たちで運営する:
- 設計事務所自身が事業主として、企画・設計から運営までを一貫して行う(例:自社で設計したコワーキングスペース、賃貸住宅、カフェなどを運営)。
「設計×運営」を始めるメリット
設計事務所がこの新しい分野に挑戦することには、たくさんのメリットが考えられます。
- メリット1:設計の想いを形にし、育てていける
- 運営に主体的に関わることで、設計に込めたコンセプトや空間の良さを、日々の活動を通して実現し、さらに良くしていくことができます。
- メリット2:クライアントへの提供価値がアップする
- 「建てて終わり」ではない、長い目で見た提案ができるようになり、クライアントからの信頼も深まります。
- 運営のノウハウを持っていることは、他の設計事務所との差別化にもつながります。
- メリット3:経営の安定につながる可能性
- 設計の仕事量に左右されにくい、継続的な収入(ストック収入)を得られる可能性があります。
- メリット4:スタッフのスキルアップとやりがい向上
- 設計以外の様々な経験は、スタッフの視野を広げ、新しいスキルを身につける良い機会になります。
- 自分たちが設計した空間が実際に使われ、活気づいているのを見るのは、大きなやりがいになるでしょう。
- メリット5:社会や地域への貢献を実感できる
- 運営を通じて、利用者や地域の人々と直接関わることで、まちづくりやコミュニティづくりに貢献している実感が得やすくなります。
乗り越えたい課題と大切な視点
もちろん、新しいチャレンジには、乗り越えるべき課題もあります。
- 課題1:運営のノウハウを身につけること
- 事業計画、収支管理、マーケティング、人の管理など、設計とは違う知識やスキルが必要です。
- 課題2:事業のリスクを理解すること
- 施設の運営には、空室が出たり、収支が計画通りにいかなかったりするリスクも伴います。
- 課題3:両立できる体制をつくること
- 設計の仕事と運営の仕事をうまく両立させるための、人員配置や仕事の進め方を考える必要があります。
これらの課題に取り組む上で、次のような視点が大切になります。
- 視点1:まずは小さく始めてみる(スモールスタート)
- 最初から大規模にではなく、比較的小さなプロジェクトや、コンサルティング業務から試してみる。
- 視点2:パートナーを見つける(外部連携)
- 運営の専門家や、経験豊富な事業者と協力することも有効な手段です。
- 視点3:学び続ける姿勢を持つこと
- 関連セミナーに参加したり、本を読んだり、事例を研究したりして、運営に関する知識やスキルを継続的に学んでいく。
まとめ:未来の設計事務所像を描くために
「設計×運営」は、単に仕事の幅を広げるだけでなく、設計事務所が社会の変化に対応し、その価値を高め続けるための重要な選択肢となり得ます。
全ての事務所が運営まで行う必要はありませんが、「設計のその先」にある運営という段階を意識し、そこに関わることを考えてみるのは、今後の事業展開において大きな強みとなるはずです。
自社の強みや状況に合わせて、「設計×運営」という新しい可能性を探ってみてはいかがでしょうか。
それは、設計事務所自身の未来、そして建築界全体の未来を、より豊かで持続可能なものにしていくための一歩となるかもしれません。