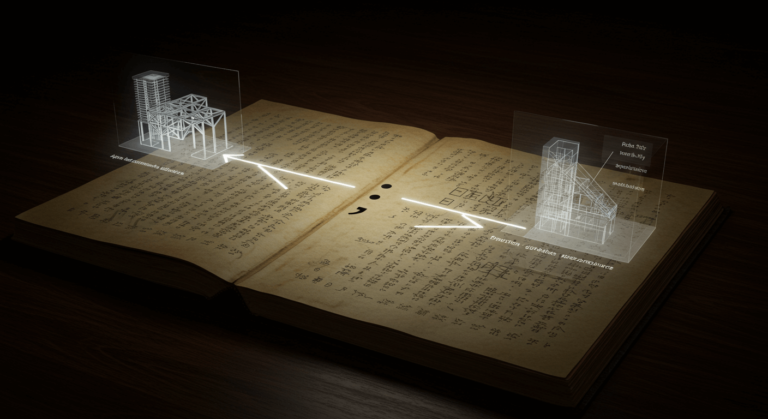設計実務に携わる皆さん、こんにちは!建築基準法って、本当に奥が深いですよね。
特に条文のちょっとした言葉の違いが、設計の解釈に大きく影響することも。
今回は、その中でも建築基準法施行令第107条(耐火性能)と第107条の2(準耐火性能)に注目します。
この記事で詳しく見ていくこの二つの性能の違い、結論からお伝えすると、ポイントは以下の通りです。
では、なぜこのような結論に至るのか、読点の後の言葉遣いに着目しながら、条文のニュアンスと設計へのヒントを一緒に深掘りしていきましょう!
条文を比べてみよう!読点とその後ろの言葉が描く、ちょっとした違い
まずは、話題の中心となる条文の表現をチェックしてみましょう。(条文のポイントが分かりやすいように、少し整理してご紹介しますね。実際の設計では、必ず原文にあたってください!)
建築基準法施行令 第107条(耐火性能に関する技術的基準)第一号(こんな感じのことが書いてあります)
「…通常の火災による火熱が…時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。」
建築基準法施行令 第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)第一号(こちらも、こんな感じ)
「…通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ…時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。」
どうでしょう?両方とも「火熱が加えられた場合に、」という読点がありますよね。
でも、その読点のすぐ後!ここからが違うんです。
ところが、第107条の2は、読点のすぐ後に「加熱開始後それぞれ…時間において」という、なんだか時計を気にするようなフレーズが入ってから、「損傷を生じないこと」と続くんですね。
これって、単なる言葉の綾なんでしょうか?それとも、もっと奥深いメッセージが隠されているんでしょうか?
意味合いのグラデーション:性能に求められる「らしさ」って?
この表現の違い、実は耐火性能と準耐火性能という二つのキーワードが持つ、それぞれに求められる「らしさ」の違いを、うまく映し出しているんじゃないかと思うんです。
第107条(耐火性能)が醸し出す雰囲気: こちらは、定められた火災のシナリオで、一定時間が経った「結果として」、建物が深刻なダメージを受けていない、という「頼もしさ」を求めている感じ。火にじっくり耐え抜く、建物の底力そのものが試されている、そんなイメージです。
第107条の2(準耐火性能)が醸し出す雰囲気: 一方こちらは、「加熱開始後」というスタートラインと、そこから「~時間において」という具体的な“時間枠”をはっきりさせることで、その決められた時間内でのパフォーマンスをきっちり求めている感じ。例えば、火事が起きた初期に避難する時間をしっかり確保するとか、あるエリアに火が広がるのを食い止めるといった、よりシャープで戦略的な役割を期待されているのかもしれませんね。時間を意識したミッション、というわけです。
つまり、読点とそれに続く言葉の組み立て方の違いは、ただ単に時間の長さを言っているだけじゃなくて、求められる性能の「キャラクター」や「活躍する場面」について、法の隠れたメッセージを伝えている可能性があるんです。
設計の現場ではどう活きる?この「深読み」の使いどころ
じゃあ、このちょっとマニアックな条文の読み解きが、私たちの普段の設計の仕事にどう役立つんでしょうか?
-
「なるほど!」が増える材料選び・工法選び: 条文が求める性能のニュアンスをしっかり掴めると、材料や工法を選ぶときに、「これだ!」という納得感がグッと増すはずです。コストと性能のいいとこ取りを狙うときにも、きっと役立ちますよ。
-
審査や確認の場で、話がスムーズに: 設計の根拠を説明するとき、こんな条文の構造まで理解していると、「なるほど、そういうことですね」と、相手にも伝わりやすくなります。ちょっとした“法規の翻訳家”気分ですね。
-
見えないリスクを避けるヒントに: 解釈が少し分かれそうな条文に出会ったら、「安全第一でいこう」とか、「この解釈で大丈夫な理由をしっかり固めておこう」とか、前もって手を打てますよね。読解力を磨くことは、転ばぬ先の杖にもなるんです。
-
設計の「引き出し」が増えるかも: 法律って、ただのルールブックじゃないんです。その裏にある安全への想いや技術的な考え方まで読み解こうとすると、設計者としての視野が広がって、新しいアイデアが生まれるきっかけになるかもしれません。
最後に、もう一度結論を:2つの性能、ここがポイント!
さて、ここまで令第107条と第107条の2の条文の奥深さを見てきましたが、最後に改めて、この二つの性能が求めるものの違いをまとめておきましょう。
このポイントを押さえて条文と向き合うことで、日々の設計業務における法規解釈が、よりクリアで、そして面白みのあるものになるはずです。
法規との「対話」を楽しみながら、これからも素晴らしい建築を創り出していきましょう!