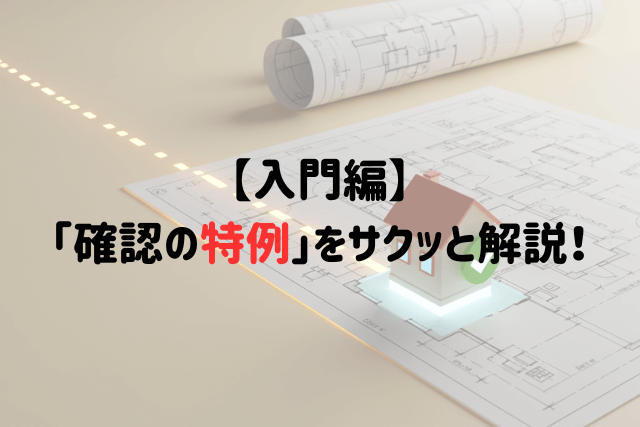建築物を建築するときは、原則、「建築確認」が必要になります。
「なんだか難しそう…」 「時間も費用もかかりそう…」
なんてイメージ、ありませんか?
でも、もしこの建築確認が少しスムーズに進むとしたら、嬉しいですよね。
実は、建築基準法には、そんな願いを叶えてくれるかもしれない「確認の特例」という制度があるんです。
今回は、このちょっと気になる「確認の特例」について、なるべく噛み砕いて、分かりやすくお話ししていこうと思います!
そもそも「建築確認」って何だっけ?
本題に入る前に、ちょこっとだけ「建築確認」そのものについておさらいです。
私たちが建物を建築する際、
その計画がちゃんと法律(建築基準法とか、いろいろあります)を守っているか、
役所や指定確認検査機関にチェックしてもらう必要があります。
これが「建築確認」です。
安全で、安心して利用できる社会基盤をつくるために、とっても大切な手続きなんです。
で、「確認の特例」って、一体なあに?
さて、いよいよ本題の「確認の特例」。
これは、建築基準法の第6条の4っていうところに書かれているルールです。
すごく簡単に言うと、
「ある条件をクリアした建物については、建築確認のチェック項目を一部省略してもOKですよ」
というもの。
これにより、手続きが少しスピーディーになったりするかもしれない、というわけです。
どんな建物なら「特例」の対象になるの?
じゃあ、どんな建物ならその「特例」の恩恵を受けられるんでしょうか?
大きく分けて、次の 3つのパターン があります。
1.国のお墨付き素材を使った建築物
- これは、あらかじめ国が「この材料なら品質も性能もバッチリ!」と認めた建築材料(専門用語で「認定型式」って言います)を使って建築する場合です。
- 安心感が違いますよね。
2.一部に国認定パーツを使った建築物
- 建築物全体じゃなくても、例えば柱や壁といった一部分に、国が認めたパーツ(工場生産された部材などをイメージすると分かりやすいかもしれません)を使用している場合も対象になります。
3.建築士がしっかり設計した特定の小規模建築物
- これは、建築のプロである建築士が設計した、比較的小さめの建築物が当てはまります。
- 具体的には「法第6条第1項第三号に掲げる建築物」というもので、例えば、特定の構造や規模の建築物などがこれに該当することがあります。
審査が軽くなるって、どういうこと?
「やった!審査が楽になる!」
と喜ぶのは、まだ少し早いかもしれません。
この特例、「ぜんぶ免除!」というわけではないんです。
省略されるのは、法律で細かく定められたチェック項目のうち、
「政令で定める規定(具体的には、建築基準法施行令第10条に定められる特定建築基準等に関する規定など)」
という部分だけ。
これは、
「建築士の技術レベルや、建物の場所、つくり、用途なんかを考え合わせると、ここはいちいち細かくチェックしなくても、安全や火事対策、衛生面で問題ないよね」
と判断される部分のことです。
つまり、
プロの建築士がちゃんと見ていて、品質も一定以上確保されているような部分や、もともとリスクが低いと考えられる小規模な建築物については、
審査のポイントを絞って、手続きを効率的にしましょう、という考え方なんですね。
嬉しいメリット、あるの?
この特例が使えると、どんないいことがあるんでしょうか?
- 手続きがスピードアップするかも!
- チェック項目が減れば、その分、建築確認済証が出てくるまでの時間が短くなる可能性があります。これは嬉しいポイントですね。
- もしかしたら、コストもちょっと抑えられる?
- 手続きが早く終われば、それに伴ってかかる費用が少し軽くなることも期待できるかもしれません。
でも、ちょっと待った!注意点もチェック
いいことずくめに見える特例ですが、いくつか知っておいてほしい注意点もあります。
- 「全部スルー」じゃない!
- 繰り返しになりますが、あくまで省略されるのは審査の一部だけ。
- 基本的な安全性に関わる大事なチェックは、もちろん行われます。
- 建築士の責任は重大!
- 審査が一部簡略化されるということは、その分、設計を担当した建築士の責任がより一層重要になる、とも言えます。
- 法律を守ったちゃんとした設計がされていることが大前提です。
まとめ:「確認の特例」を賢く使うために
建築基準法第6条の4に定められた「確認の特例」。
これは、建築確認の手続きを少しでもスムーズにするための、いわば「近道」のような制度です。
特に、
- 国が認めた建材や部材を使用するケース
- 建築士が設計する特定の小規模な建築物
などが対象となります。
この特例も活用しつつ賢く情報を集め、スムーズで安心な建築計画を実現しましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね。