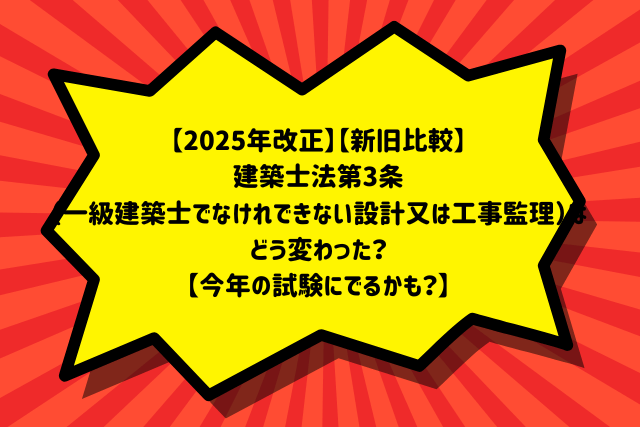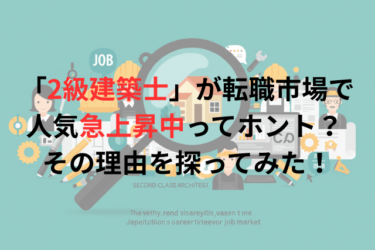今回は、法改正の中でも特に大事な「建築士法第3条(一級建築士でなけれできない設計又は工事監理)」の改正について、一緒に見ていきたいと思います。
建築士試験で問われる可能性も高いポイントなので、この機会に、改正のポイントをしっかりつかんでおきましょう。
✅ 木造・非木造どちらも、高さのルールが「13m/軒高9m」⇒「高さ16m/地階を除く階数が4以上」に見直され、より分かりやすくなりました。
✅ これによって、二級建築士が設計・工事監理できる建物の規模が広がります。
✅ これによって、二級建築士が設計・工事監理できる建物の規模が広がります。
目次
【新旧比較】法第3条 ここが変わりました!
一級建築士でなけれできない設計又は工事監理の範囲について、以下の点が新しくなりました。
| 号 | 構造 | 新ルール(改正後) | 旧ルール(改正前) |
|---|---|---|---|
| 第二号 | 木造 | 高さ 16m超 又は 地階を除く階数が4以上 | 高さ 13m超 又は 軒高9m超 |
| 第三号 | RC造 S造等 | 高さ 16m超 又は 地階を除く階数が4以上 (延べ面積300㎡超の場合) | 高さ 13m超 又は 軒高9m超 (延べ面積300㎡超の場合) |
【ポイント解説】実務で知っておきたいこと
実務に直結する変更点を、ポイントごとに整理していきましょう。
1. 高さや階数のルールが変わりました
・これまでのルール:高さ13m超または軒高9m超
・これからのルール:高さ16m超または地階を除く階数が4以上
➡️ ポイント
判断が少し分かりにくかった軒高9mの基準がなくなりました。
高さの基準が16mに引き上げられ、判断しやすい「地階を除く階数が4以上」という基準が新しく加わりました。
判断が少し分かりにくかった軒高9mの基準がなくなりました。
高さの基準が16mに引き上げられ、判断しやすい「地階を除く階数が4以上」という基準が新しく加わりました。
2. 木造の建物ではこんな影響が
➡️ 活躍の場が広がります
これまで一級建築士の専門業務だった以下の規模の木造建築物を、二級建築士や木造建築士も担当できるようになります。
これまで一級建築士の専門業務だった以下の規模の木造建築物を、二級建築士や木造建築士も担当できるようになります。
高さ13m超~16m以下 かつ 地階を除く階数が3以下のもの
➡️ 例えばこんな建物
高さ14.5m、木造3階建て(地階なし)の事務所ビル
高さ15.0m、大屋根を持つ木造3階建て(地階なし)の店舗
3. 鉄骨造(S造)やRC造の建物では
➡️ ルールが分かりやすくシンプルに
木造と同じ「高さ16m超 or 地階を除く階数が4以上」という基準に統一されました。
これで、建物の構造によって高さの基準が違う、ということがなくなり、よりシンプルになりました。
木造と同じ「高さ16m超 or 地階を除く階数が4以上」という基準に統一されました。
これで、建物の構造によって高さの基準が違う、ということがなくなり、よりシンプルになりました。
【改正の背景】
今回の改正が目指しているのは、主にこの2つです。
- 新しい技術を活かすため: CLT(直交集成板)など、最近の中大規模木造建築の技術の進歩を、きちんと制度に反映させています。
- 木の利用をもっと広げるため: 設計や工事のプロセスをスムーズにすることで、木の利用を後押しし、環境にやさしい社会づくりにもつなげています。
【最後に】
今回の法第3条の改正は、特に二級建築士にとって、活躍のフィールドが広がることを意味します。
高さと「地階を除く階数」という客観的な指標に整理されたことで、今まで以上に色々な木造建築にチャレンジしやすくなりますね。
関連記事
2級建築士のニーズが高まっている理由 (1)1級建築士の獲得が難しくなっている (2)2級建築士の業務範囲である低層建築やリフォームの仕事が増えている (3)25年4月の脱炭素大改正で確認申請業務の負担が増している (4)1級建[…]