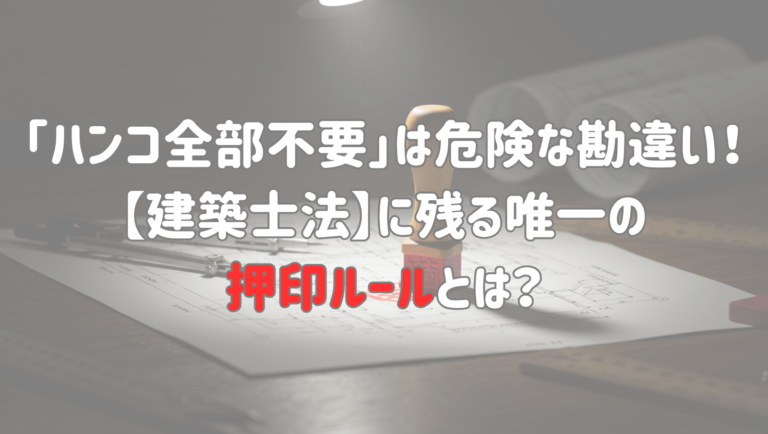「もうハンコは要らないよね?」
そう思っている建築士の皆さん、 ちょっと待ってください! ⚠️
99%の書類はその通りですが、残り1%… 今も「記名押印」が法律で定められている超重要なケースがあるんです。
✅ その具体的な条件が【チェックリスト】で一目瞭然
✅ なぜそのルールだけが残っているのか【理由】に納得できる
では、さっそく見ていきましょう!
【結論】押印が必要なのは、この契約書だけ!
色々考える前に、まず結論からお伝えします。 建築士法で「記名押印 or 署名」が求められるのは、これだけです。
📄 建築士法 第22条の3の3
これは、特定の条件を満たす「設計・工事監理の契約書」に関するルールです。
設計図書や工事監理報告書の話ではありません。 あくまで建築主と交わす「契約書」の話、と覚えてください。
【あなたの業務は大丈夫?】30秒チェックリストで確認!
「じゃあ、自分の担当業務は関係あるの?」 そう思ったら、この3つの質問にYES/NOで答えてみてください。
契約前の30秒チェック!✅
Q1. 建築物の延べ面積は【300㎡】を超える?
→ YES / NOQ2. プロジェクトは【新築】?
→ YES / NOQ3. これから交わすのは【設計】または【工事監理】の契約?
→ YES / NO
いかがでしたか?
もし、3つすべてに「YES」と答えたなら… その契約書は、今回のルール対象です!👇
【重要】契約書で求められる2つのアクション
3つのチェックがすべてYESだった場合、その契約書には法律に基づき、当事者(建築士事務所と建築主)が以下のどちらかを行う必要があります。
選べるアクションは2つ!
1. 記名 + 押印 ✍️ (PC入力やゴム印の名前 + ハンコ)
2. 署名 ✒️ (自筆のサイン。この場合はハンコ不要!)
自筆でサラサラっとサインすればハンコは要りません。 名前をPCで印刷した場合は、ポンっとハンコが必要。 この2択です!
【なぜ?】このルールだけが生き残った理由
ここで、新人建築士くんの疑問を見てみましょう。
新人くん 👨💻 「先輩、なんで設計図書はハンコが要らないのに、契約書だけこんなに厳しいんですか?」
ベテランさん 👩🏫 「いい質問ね!それは、書類の『相手』と『目的』が違うからなのよ。」
- 設計図書など
- 相手:建築士自身(の責任)
- 目的:技術的な正しさを証明するため
- → デジタル化で効率UP!記名で責任は明確。
- 契約書
- 相手:お客様(建築主)
- 目的:お互いの『本気の合意』をカタチに残すため
- → 重大な約束事だから、より慎重な本人確認(署名 or 記名押印)が必要!
納得ですね! お客様との大切な約束だからこそ、法律も慎重な手続きを求めているのです。
【まとめ】今日のポイントをもう一度
最後に、今回の重要ポイントをおさらいします。
- ✅ 原則:建築士の押印義務は、ほぼなくなった。
- ⚠️ 唯一の例外:300㎡超の新築における設計・工事監理契約書。
- ✍️ 対応:その契約書には「署名」か「記名押印」を!
「脱ハンコ」の流れの中でも、この唯一の例外ルールは、お客様との大切な約束事を守るための重要な手続きです。
法改正の内容を正しく理解し、自信を持って日々の業務を進めていきましょう!