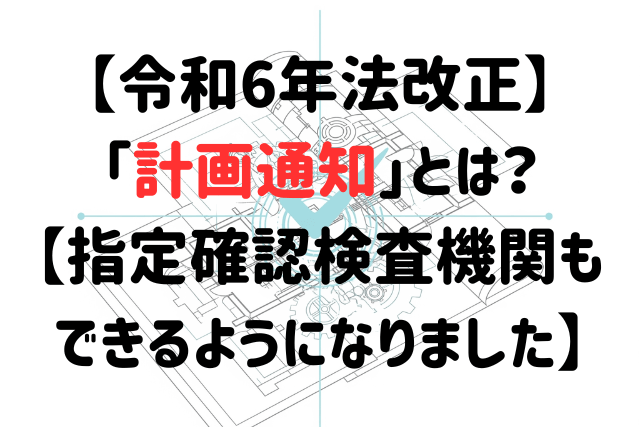こんにちは!
「計画通知」という言葉、耳にしたことはありますか?
この記事では、建築基準法第18条に基づく「計画通知」制度について、令和6年(2024年)改正のポイントを交えて、目的・手続き・注意点を解説します。
計画通知とは何か?
建物を新築したり、大規模に改修したりする際、通常、民間建築物には「建築確認申請」が必要です。
しかし、国、都道府県、または建築主事を置く市町村が建築主となる建築物については、確認申請の手続きが適用されません。
その代わりに、建築基準法第18条で定められているのが「計画通知」という手続きです。
では、なぜ役所の建物には特別なルールがあるのでしょう?
これは、次のような理由からです。
- 国や地方公共団体は、もともと法律を守る立場。
- 建築基準法に詳しい専門家を多数抱えています。
- そのため、民間の建物と同じ確認手続きを求める必要が少ないと考えられています。
つまり、計画通知は、 「行政機関が、自分たちの建物の計画を、工事を始める前に建築主事などに知らせて、審査してもらうことで、法律に合っているかを確認する」ための制度です。
計画通知が必要な建物とは?
計画通知が必要になるのは、次のいずれかが建物の持ち主になる場合です。
- 国の機関
- 都道府県
- 建築主を置く市町村
これらのところが、新しく建物を建てたり、大きく直したり、模様替えしたりするときが当てはまります。
(ただし、例外もあります。
防火地域や準防火地域以外で、増築や改築、移転をする場合で、床面積の合計が10平方メートル以内なら計画通知は不要です(法第18条第2項ただし書き)。
これは、小さな工事なら、周りへの影響も少ないからですね。)
計画通知のステップ詳細
計画通知の手続きは、次の流れで進みます。
1. 計画の通知(工事前)
工事を始める前に、建物を建てる国の機関の長、都道府県知事、または市町村長などは、その計画を所管の建築主事等に通知します(第18条第2項)。 これは確認申請で言う「申請」にあたるものです。
2. 審査と確認済証の交付
- 通知を受けた建築主事等は、計画が建築基準関係規定に適合しているかを審査します。
- 適合と認めた場合には「確認済証」を交付(第18条第3項)。
- この証明が出て初めて、工事ができるようになります。
💡 令和6年改正のポイント
- 2024年11月1日施行の改正法により、指定確認検査機関も計画通知の審査・検査業務をできるようになりました(第18条第4項)。
- これにより、民間の専門知識も活用されるようになり、審査の効率化が進んでいます。
- そのため、建物を建てる国の機関の長、都道府県知事、または市町村長などが、工事を始める前に計画を指定確認検査機関に通知した場合、その指定確認検査機関が計画が法律に合っているかを審査し、問題ないと認められれば確認済証を交付します。
3. 構造計算適合性判定(必要な場合)
- 高度な構造を伴う建築物では、構造計算適合性判定が求められます(第18条第5項以降)。
- この場合、建物を建てる国の機関の長、都道府県知事、または市町村長などが、都道府県知事に判定を依頼し、判定結果を受けてから確認済証が交付されます。
4. 工事着手と完了報告
- 確認済証を得るまで、工事に着手できません(第18条第17項)。
- 工事完了後は、4日以内に完了通知を建築主事等へ行う必要があります(法第18条第20項)。
5. 完了検査と検査済証
- 建築主事等は完了通知を受けてから7日以内に検査を行い、基準に適合していれば「検査済証」が交付されます(第18条第21~22項)。
6. 中間検査(特定工程がある場合)
- 一部の工事では中間検査が必要です。
- 該当する工事が終わった時点で通知し、合格すれば「中間検査合格証」が交付されます(第18条第28~30項)。
7. 仮使用の特例
- 大型建築物などでは、検査済証を受ける前に一時使用が認められる場合があります(第18条第38項)。
- ただし、安全性や避難上問題がないと所管行政が判断した場合に限ります。
さいごに
「計画通知」は、国や地方公共団体が建築物を建てる際に義務付けられた特別な手続きです。
令和6年(2024年)の法改正により、指定確認検査機関も計画通知の審査・検査業務をできるようになりました。
建築の世界も常に進化しています。
新たな知識を取り入れ、個人個人のレベルアップを図りましょう!
この情報が、皆さんの日々の業務の一助となれば幸いです。