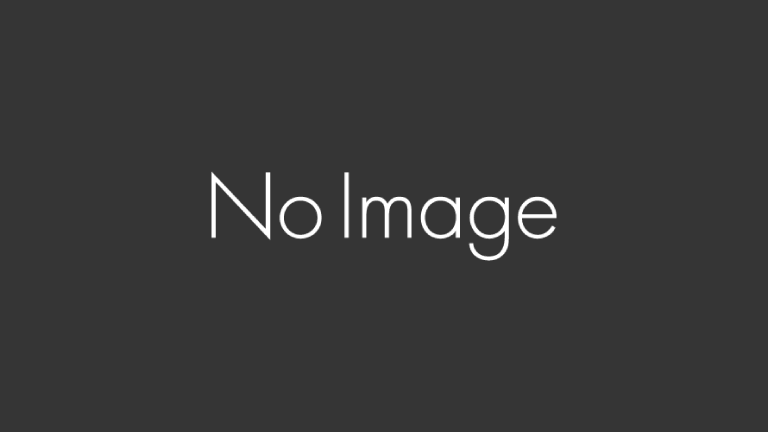お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
毎日暑い日が続いていますが、夏バテしていませんか?
私は、夏バテ気味で毎日炭酸飲料三昧です(笑)
今回は、私も持っている資格
「一級建築基準適合判定資格者」について詳しく説明していきます。

建築基準適合判定資格者とは?
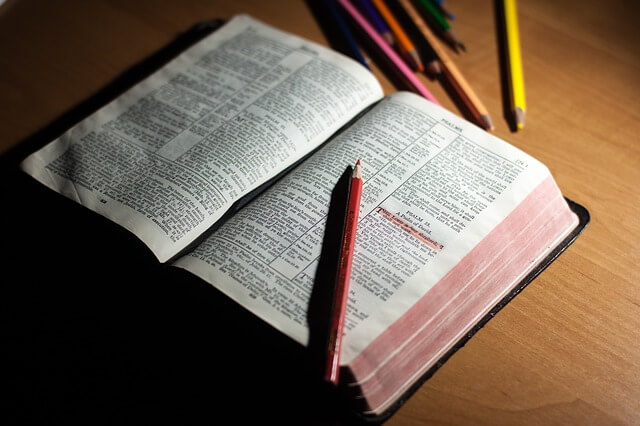
建築計画が、建築基準法や関係法令に適合しているか否かの確認や検査を行う資格者のこと
例えば、
建物を建てるとき確認申請をします。
その際、建築基準適合判定資格者が建築基準法に適合しているか
確認をしないと確認済証は交付されません。
また、中間検査や完了検査においても
この建築基準適合判定資格者が法に適合しているか検査し
適合していなけば検査済証は交付されません。
つまり、
建てることができる建物なのか判断をすることができるのが
建築基準適合判定資格者なのです。
受検資格は?

ここを知りたい人が多いと思います。
法改正
(建築基準適合判定資格者検定)
第五条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。
2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。
3 一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
4 二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。
5 一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。
6 二級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。
つまり、受検できるのは
です。
ちなみに、受検をするにあたっては、実務経験は必要ではありません。
一級の資格をもっていればいいのです。
【重要】登録の要件
ここが大事です。
(登録)
第七十七条の五十八 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、国土交通大臣が、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
つまり、
↓下記は、法改正前の内容です。
建築基準法第5条第3項に規定されています。
一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務その他これらに類する業務で次に揚げるもののいずれかに関して、2年以上の実務経験を有するものに限られます。
(1)建築審査会の委員として行う業務
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
(3)建築物の敷地、構造又は建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務を除く。)であって国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの(平成11年6月3日建設省告示第1314号として規定)
簡単にいってしまうと
↑読み方注意!

合格率
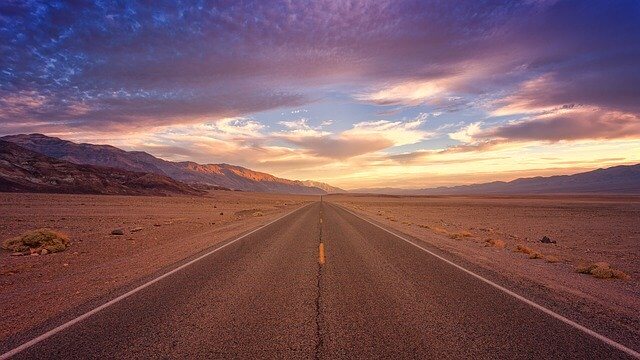
| H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06(8/30) | R06 (12/30) |
|
| 実受検者数 | 1,134 | 1,032 | 1,178 | 1,314 | 1,393 | 1,300 | 1,299 | 1,161 | 1,108 | 938 | 933 | 983 | 890 | 984 | 340 |
| 合格者数 | 518 | 264 | 307 | 391 | 496 | 324 | 461 | 461 | 352 | 274 | 272 | 354 | 318 | 377 | 152 |
| 合格率 | 45.7% | 25.6% | 26.1% | 29.8% | 35.6% | 24.9% | 35.5% | 39.7% | 31.8% | 29.2% | 29.2% | 36.0% | 35.7% | 38.3% | 44.7% |
※令和6年一級建築基準適合判定資格者検定について、中止会場の受検者及び台風10 号の影響による欠席者を対象とし、再検定が実施されました。
(国土交通省HPより)
合格率はだいだい30~40%です。

難易度

ぶっちゃけ一級建築士試験の方がはるかに難しいです。
一級建築士の難易度を★★★★★とすると
建築基準適合性判定資格者は、★★★くらいです。
ちなみに、私は2か月の勉強で受かりました。
知人は1か月の勉強で受かっています。
そこまで難しい試験ではありません。

一級の検定内容は?
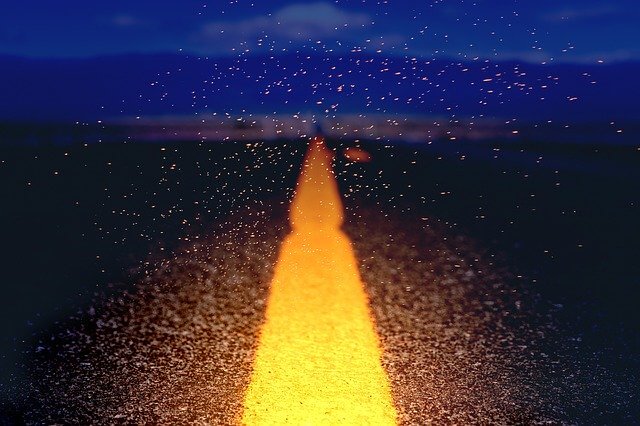
・検定日は、毎年8月最後の金曜日です。平日です。日曜日ではないので注意!
・検定料は、一級は3万円です。ちょっと高めです。
ただし、市町村又は都道府県の職員は免除されます。
もともと確認検査は行政のみの仕事だったのでその流れで現在でも行政職員は免除されているのだと思います。
(このことを行政の人に言ったら驚いてました。)
・午前中に考査A、午後に考査Bが行われます。
法令集、告示、電卓を持ち込むことができます。
法令集の線引きについては、建築士試験と準ずるとなっています。
詳しくはこちらをどうぞ↓
【追記 令和3年4月2日】 令和3年度も、令和2年度と同じ法令集の取扱いとなっているようです。 出典:建築技術教育普及センターホームページ 詳しい内容は、「センターのホームページ」 or 「このブログ」 をご覧ください[…]
【重要】令和7年は持ち込める法令集注意!!!
令和7年4月1日現在において施行されているものを適用すると発表されました。
詳しくはこちらをどうぞ↓
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。…
考査A
五肢択一式です。
1時間25分で17問を解きます。
確認検査や違法建築物に対する措置に関する問題が中心です。
よって、確認検査に関係の無い建築士法や建設業法は出題されません。
難易度は、一級建築士の法規の試験よりは少し難しめになっていますが、
過去問を練習しておけば大丈夫です。

考査B
・建築計画1
・建築計画2
・建築計画3(構造審査)
の3つに分かれています。
解答時間は、3時間25分です。めちゃくちゃ長いです。

・建築計画1、2
図面が与えられていて、審査対象項目について実際に審査します。
この審査を記述で書かなければなりません。
理由を書き、さらに根拠規定を第○○条第〇項など書かなければなりません。
全部文章で答えるので、めちゃくちゃ文字を書きます。製図同様めちゃくちゃ書きます。
つまり、腱鞘炎になるくらい書くことが多いです。これが検定の一番厳しいところです。
(パソコンが使えたらいいのにって思います。)
また、
根拠規定は第○○条と書けばいいのですが、
理由の書き方は、過去問で何度か練習しておかないとなかなか書けません。
一級建築士の製図試験の記述のように型を覚えるのが手っ取りばやいです。
・建築計画3(構造審査)
計画の概要が与えられていて、審査対象項目について実際に審査します。
普段構造の審査をしてない人にとっては、難しいです。
なので、過去問を解けるようにするくらいしか対策はありません。
実際ぼくが受けたときは、過去問と全然違う内容で、お手上げ状態でした。
ただ、根拠条文と判定結果だけは書きました。
つまり、何が言いたいかというと
分からなくても、何かしら書きましょうってことです。
全然印象が違いますし、それで1点でももらえれば儲けものです!

何としてでも1点でいいから取りに行く!
過去問の入手方法

入手方法は2つです。
①国土交通省のHP
②建築行政情報センターのHPから購入
①国土交通省のHPには過去問が記載されています。
考査Aについては、問題と解答があります。解説はありません。
また、考査Bについては、図面と設計条件のみ掲載されています。問題や解答解説はありません。
なので、勉強には適していません。
適判を受ける人のほとんどが、②建築行政情報センターのHPから購入することになります。
こちらには、問題から解答解説まで載っています。
私もここで購入して勉強しました。
適判を受ける方はまずはこの過去問集をゲットしましょう!

最後に
以上、【法改正対応済み】一級建築基準適合判定資格者の「受検資格」・「過去問入手法」・「勉強法」【2か月で受かる!】でした。
難易度はそこまで高くありません。
しかし、受検資格の関係により受検者数が少ないため、レアな資格になっています。
受検資格がある人は、是非ともチェレンジしてみましょう!
行政の方は、定年後再就職先の幅が広がり、
民間の方は、転職しやすくなりますよ!

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans )です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます! 今回は、【体験談】適判を受けた時にビビったこと を書いていきたいと思います。 &nb[…]
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 いよいよ2021年8月27日(金)は、建築基準適合性判定資格者検定ですね。 検定を受け[…]