お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
突然ですが、まずこの↓写真を見てください。

どこにでもある普通の住宅です。
なぜ屋根が「勾配」になっているのでしょうか?
考えてみてください。
・屋根に雨水がたまらないようにするため
・雪が屋根に積もらないようにするため
・デザイン的にかっこいいから
などが考えられると思います。
しかし、実は、これだけでなく、勾配屋根になるのは、法的な理由があるのです。
その1つが、「道路斜線」です。
で、「勾配屋根になる法的な根拠」、つまり、「道路斜線の計算方法」を先に言っちゃうと、
高さ≦L×1.25or1.5
です。
では、条文を用いてサクッと解説していきます。

【道路斜線の条文】
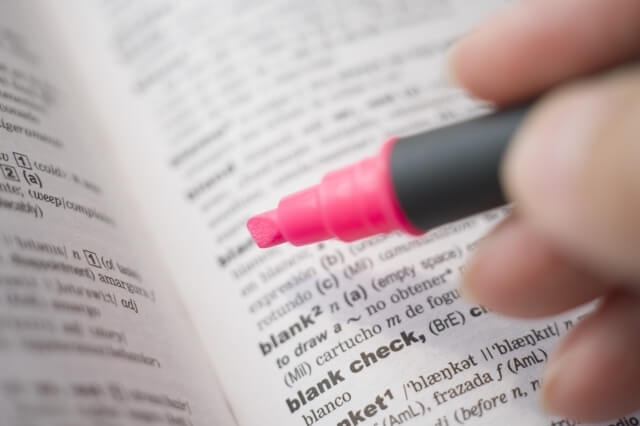
建築基準法第56条第1項第一号です。
建築物の各部分の高さは、次に揚げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)及び(ろ)に揚げる地域、地区又は区域並びに容積率の限度に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に揚げる距離以下の範囲内において、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に揚げる数値を乗じて得たもの。
解説
重要なところに、赤と黄色でマーカーを引いてみました。
そこをまとめると、
建築物の各部分の高さ≦「前面道路の反対側の境界線からの水平距離L」×「同表(に)欄に揚げる数値」
この式を満たせばいいのです。
これが、道路斜線の基本中の基本です。
また、
「同表(に)欄に揚げる数値」を簡単にまとめると、
| 住居系の用途地域 | 1.25 |
| 住居系以外の用途地域 | 1.5 |
となります。
つまり、
高さ≦L×1.25or1.5
となればいいのです。
たったこれだけです。
簡単でしょう?!

【例題】A点とB点の高さを計算してみましょう。
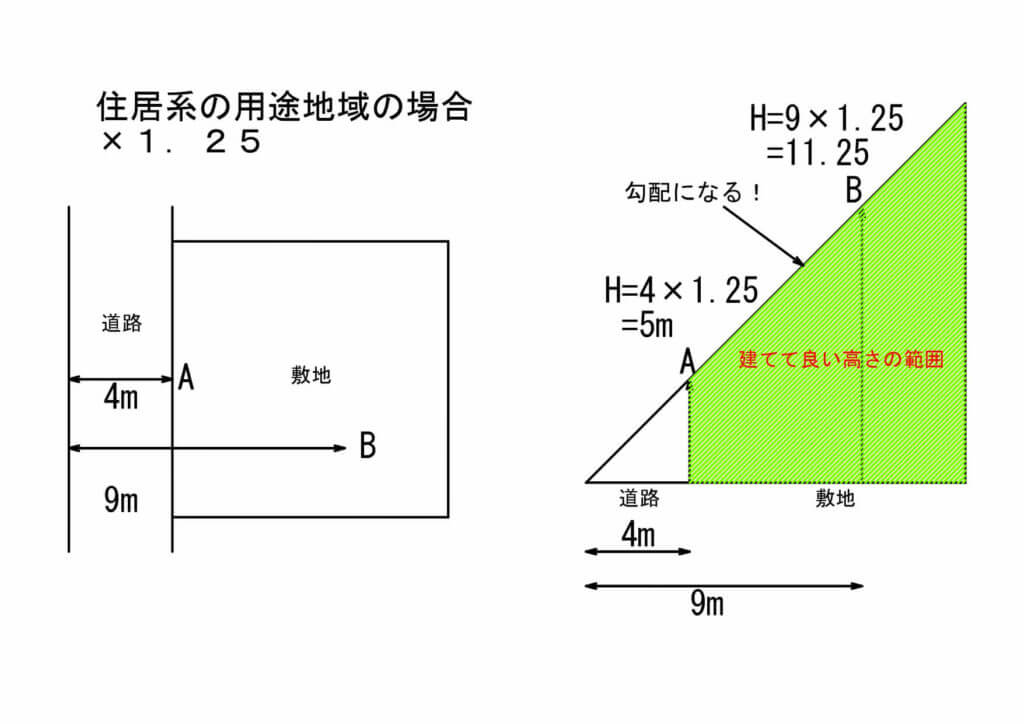
| 点Aについて ・L=4m ・掛ける数値は、1,25(住居系の用途地域の場合)よって、 H≦4m×1.25=5m つまり、 点Aは、5m以下であればOK! |
・L=9m
・掛ける数値は、1.25(住居系の用途地域の場合)よって、
H≦9m×1.25=11.25m
つまり、
点Bは、11.25m以下であればOK!
となるのです。

さいごに
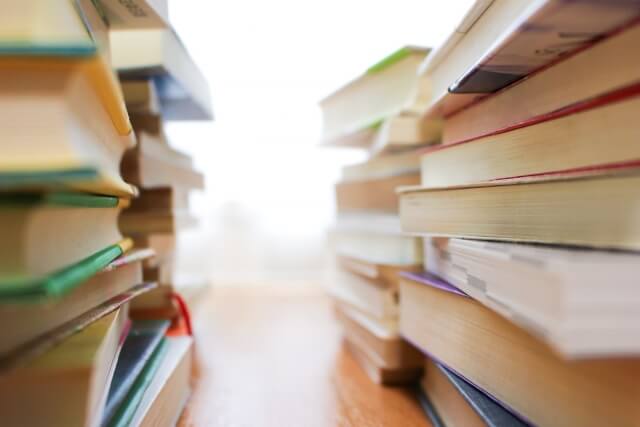
以上、【初心者向け】「道路斜線制限」をわかりやすく解説します!でした。
道路斜線の計算式は、
高さ≦L×1.25or1.5
です。
これが基本中の基本です。これは必ず押さえましょう!!!
そして、この道路斜線には、緩和規定があります。
それはまた後日解説していきたいと思います。
(この緩和規定がちょっとめんどくさいんです。)
ともかく、道路斜線の基本は、
高さ≦L×1.25or1.5
ですからね!
しつこいですが、必ず押せておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 前回は、「道路斜線」の基本について解説しました。 まだ読んでいない人は、こちらから↓どうぞ[…]
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 建築士試験の法規は、めちゃくちゃ時間がタイトですよね。 そのなかで[…]


