
結論
- 建築物移動等円滑化基準
- 義務(必ず守るルール)
- バリアフリーの基本ライン
- 建築物移動等円滑化誘導基準
- 任意(義務じゃない)
- バリアフリーの目標ライン(ワンランク上)
- クリアするとメリットがある!
こんにちは!
建物の設計や法律の勉強を始めると、なんだか似たような難しい言葉がたくさん出てきて、
「うーん、何が違うんだっけ…??」って混乱しちゃうこと、ありますよね😅
特に、バリアフリーに関係する言葉でよく聞くのが、
「建築物移動等円滑化基準(けんちくぶついどうとうえんかつかきじゅん)」 と 「建築物移動等円滑化誘導基準(けんちくぶついどうとうえんかつかゆうどうきじゅん)」 の二つ。
名前、そっくりすぎません!?(笑) でも、この二つ、実は意味が全然違う、とっても大事なポイントなんです。
この記事を読めば、このややこしい二つの違いがスッキリ分かりますよ! さっそく見ていきましょう!😊
まずは基本!「建築物移動等円滑化基準」ってなぁに?
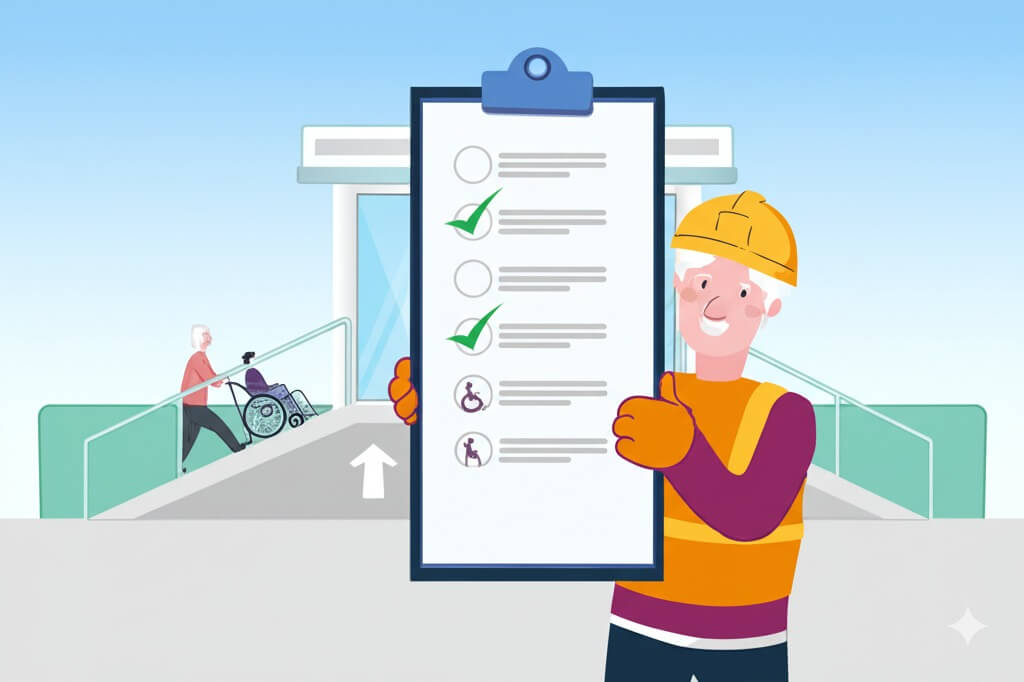
こっちは、いわば「建物のバリアフリーに関する、最低限守らなきゃいけない基本ルール」のことです。
たくさんの人が利用する建物(例えば、お店、駅、病院、役所とかね)を、ある程度の大きさ以上で新しく建てたり、大きく改修したりするときには、必ずこのルールを守らないといけません。
法律で決められている義務なんです。
「移動等円滑化」っていうのは、お年寄りや車いすを使っている方、ベビーカーを押している方、目の不自由な方など、いろんな人が建物の中をスムーズに、そして安全に移動できるようにしようね、っていう意味合いです。
具体的にどんなルールがあるかというと、例えば…
- 廊下の幅: 車いすでも通りやすいように、十分な幅(例:120cm以上)を確保する。
- 階段: 手すりをちゃんと付ける。急すぎない勾配にする。
- 段差: できるだけなくす。もし段差ができちゃう場合は、スロープを付ける。
- トイレ: 車いすでも入れる広さのトイレ(多機能トイレとか、だれでもトイレって呼ばれるもの)を設置する。
- 案内表示: どこに何があるか分かりやすいように、点字や音声案内などを付ける。
などなど、みんなが安心して建物を使えるようにするための、基本的な配慮が定められているんですね。「これは絶対にやってね!」っていう、いわばスタートラインのルールです。
ワンランク上を目指す!「建築物移動等円滑化誘導基準」って?
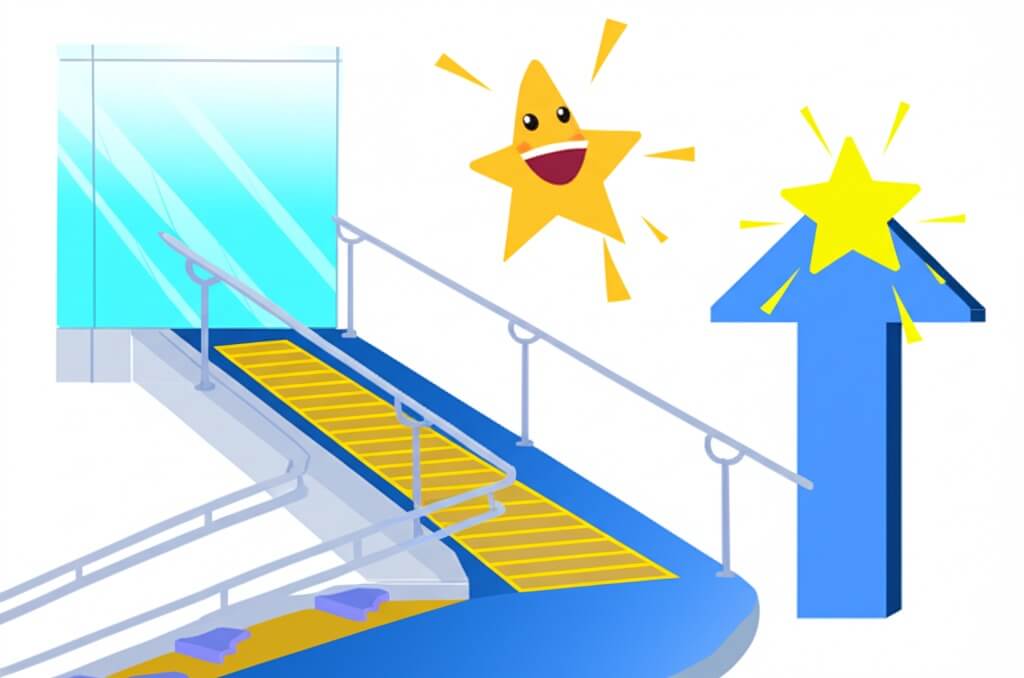
さて、お次は名前に「誘導」が付く方。 こっちは、さっきの「基準」とは違って、義務じゃありません。「絶対に守らなきゃダメ!」っていうルールではないんです。
じゃあ何なのかというと、「もっともっとバリアフリーを進めて、さらに快適な建物にするための、目指すべき目標ルール」みたいなイメージです。
国が「こっちのレベルを目指してくれると、もっと良くなるよ!ぜひ頑張ってみてね!」って誘導している感じかな?
だから、この「誘導基準」は、さっきの「基準」(義務ルール)よりも、さらにハイレベルな内容になっています。
例えば…
- 廊下の幅: 車いす同士がすれ違えるくらい、もっと広い幅(例:180cm以上)にする。
- 階段: 手すりを片側だけじゃなくて、両側に付ける。
- トイレ: バリアフリートイレを、1階だけじゃなくて、各階に設置する。
- エレベーター: より多くの人が使いやすいように、もっと配慮されたエレベーターを設置する。
どうでしょう?さっきの「基準」よりも、さらに手厚い配慮が求められているのが分かりますよね?😊
なんで「誘導基準」なんてあるの?メリットがあるから!

「義務じゃないなら、別に目指さなくてもいいんじゃない?」って思うかもしれません。 でも、わざわざこの厳しい「誘導基準」をクリアすると、いいことがあるんです!✨
建物を建てる人(建築主さん)が、「うちの建物、誘導基準をクリアするくらい、すごくバリアフリー頑張ってます!」って役所に申請して認められると(これを「認定」って言います)、例えば…
- 容積率が緩和されることがある: ちょっとだけ広い建物を建てられるようになるかも!
- 補助金がもらえることがある: 国や自治体からお金のサポートを受けられるかも!
- 建物のPRになる: 「すごく人に優しい建物ですよ!」ってアピールできる!
つまり、頑張ってハイレベルなバリアフリーを実現すれば、ご褒美(メリット)があるよ!っていう仕組みなんですね。
だから、義務じゃなくても、この「誘導基準」を目指して頑張る建物がたくさんあるんです。
まとめ:これで違いはバッチリ!
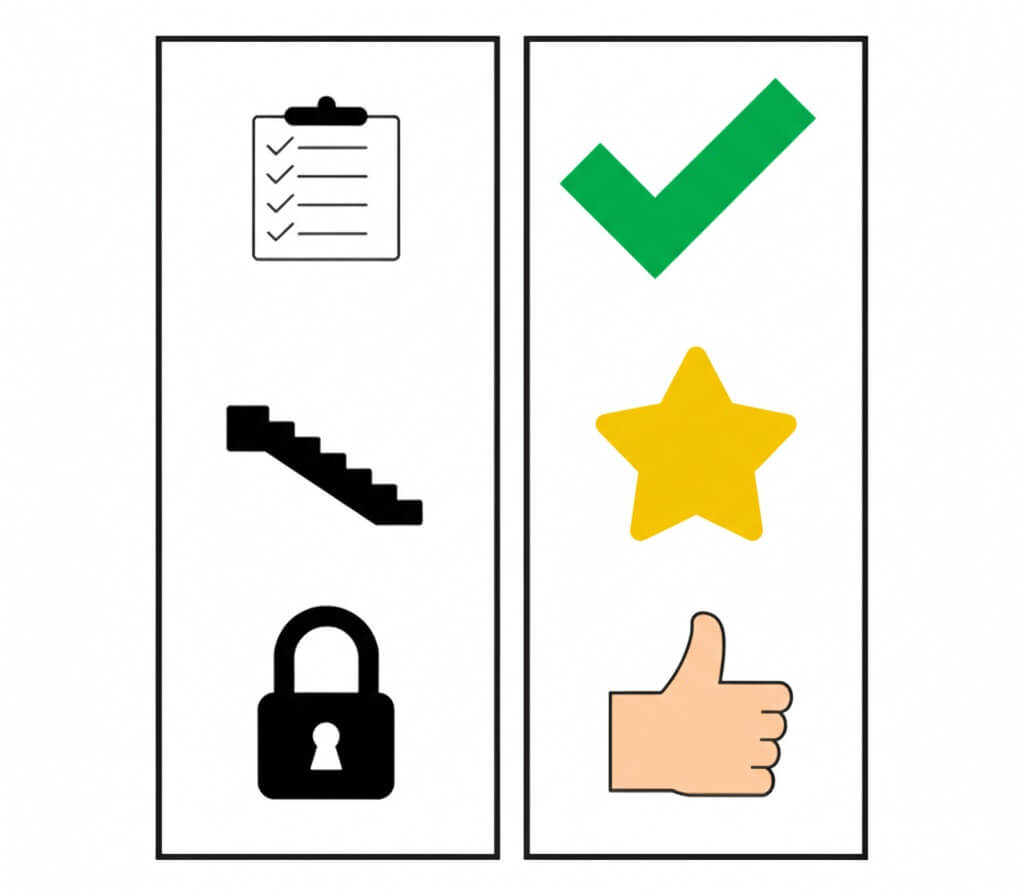
さあ、二つの「基準」の違い、スッキリしましたか?
・義務(必ず守るルール)
・バリアフリーの基本ライン
・任意(義務じゃない)
・バリアフリーの目標ライン(ワンランク上)
・クリアするとメリットがある!
この違いが分かると、建物の計画図を見たり、街の中の新しい建物を見たときに、「あ、ここのスロープは基準を満たしてるな」とか、
「お、このトイレは誘導基準レベルかも!」なんて、ちょっと見方が変わって面白くなるかもしれませんよ😉
建築の勉強、覚えることはたくさんあるけど、一つ一つ理解していくと楽しいですよね! これからも応援しています!💪
最後まで読んでくれて、ありがとうございました!
