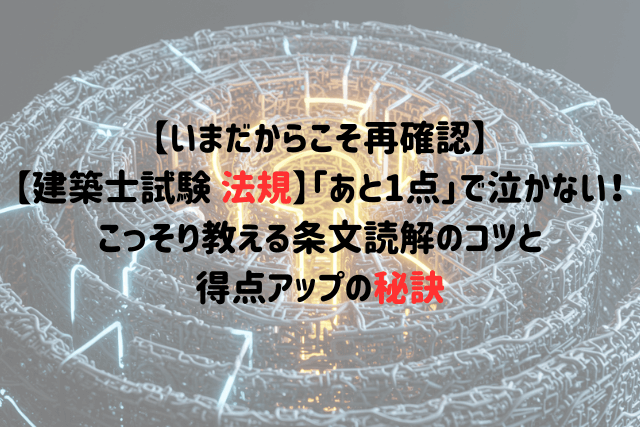建築士試験の勉強、本当に毎日お疲れ様です!
山のようなテキスト、終わらない過去問…
特に「法規」って、あの分厚い法令集を前にすると、 ちょっと気が遠くなりそうになりますよね。
その気持ち、痛いほどよく分かります。
でも、この法規こそ、 知っているか知らないか、そして「どう読むか」でグッと差がつく科目なんです。
「ちゃんと勉強したのに、なぜか点数が伸びない…」
「ケアレスミスがどうしても減らない…」
そんな悩みを抱えているあなたへ。
今日は、多くの合格者が「いまだからこそ再確認してよかった!」と口を揃える、 条文読解のちょっとしたコツと、 試験本番で「あと1点」を確実に取りにいくための大切なポイントを、 こっそりお伝えしたいと思います。
これを読めば、あなたの法規アレルギーも少しは和らぐかもしれませんよ!
試験官はここを見ている!読み間違い厳禁の「キーワード」たち(再確認!)
まずは基本の確認から。
でも、この基本が本当に大事なんです。
言葉のニュアンス一つで、天国と地獄…なんてことも。
1.接続詞:「及び」と「又は」~この違い、本当に大丈夫?~
- 「A 及び B」
- これは「A と B、両方とも」ってこと。
- 片方だけじゃダメなんです。
- 得点アップの知恵: 選択肢で「及び」を見たら、「どっちも満たしてる?怪しいぞ?」と探偵スイッチをオン!
- 「A 又は B」
- こっちは「A か B、どっちか一方でOK」(もちろん両方でもいいですよ!)。
- 得点アップの知恵: 「又は」なら、選択肢の幅が広がるチャンス!「どっちか当てはまればラッキー!」くらいの気持ちで。
この二つ、試験会場で焦っていると、意外と見落としがち。
深呼吸して、しっかり区別してくださいね。
2.条件・例外:「ただし」「場合において」「適用しない」「この限りでない」~「ただし書き」こそドラマがある!~
- 「ただし、~」
- 出ました!最重要キーワード!
- 本文のルールに対する「でもね…」という例外。
- 「原則はこうだけど、実はこういうケースは別なんだよ」という、物語の転換点みたいなものです。
- ここを読み飛ばしたら、もう、大変なことに…!
- 「~の場合において」
- 「こんな時はね…」と、特定のシーンを切り取る言葉。
- そのシーンに自分がいるかいないかで、ルールが変わるんです。
- 「~については、適用しない」「~の場合は、この限りでない」
- 「このルール、今回はお休みです!」というお知らせ。
- 見逃すと、余計な心配をしちゃうかも。
得点アップの知恵: 条文を読んだら、「で、例外は?『ただし』はどこだ?」と探す癖をつけると、読解力が格段に上がります。
多くの場合、美味しいところ(=試験に出るところ)は、「ただし」の先に隠れていますよ。
3.範囲・程度:「以上」「以下」「未満」「超える」~その1mm、その1cm²が運命を分ける!~
- 「以上」「以下」
- その数字、含みます!
- 「未満」「超える」
- その数字、含みません!
得点アップの知恵:
「高さ31メートル以下」と「高さ31メートルを超える」では、
31メートルぴったりの建物が天国行きか地獄行きか変わってしまいます。
この微妙な違い、試験官は大好物です。
具体的な数字を当てはめて、「これはセーフ?アウト?」と自分にクイズを出すのがおすすめ。
4.定義語:その言葉、本当に「自分の言葉」で説明できる?~法規の土台を固めよう!~
- 「建築物」「特殊建築物」「大規模の修繕」「居室」… これらの言葉、普段なんとなく使ってませんか? 法規の世界では、一つ一つにちゃーんと厳密な意味(法第2条とかに書いてあります!)が決められています。
得点アップの知恵:
「なんとなく知ってる」が一番怖い!
「居室って何?」と聞かれたら、スラスラ説明できるくらいじゃないと、応用問題で足元をすくわれます。
自分の言葉で言い換えられるか、友達に説明できるか、試してみてください。
5.主体・客体:「誰が」「何を」するの?~ドラマの登場人物を把握せよ!~
- このルールは、 「誰が」(建築主?設計者?それとも…?) 「何をする」(届け出る?許可をもらう?それとも何かしちゃダメ?) って話なのか。
得点アップの知恵:
特に「設計者として、あなたはどうする?」という視点は、試験でめちゃくちゃ問われます。
常に当事者意識を持って条文を読むと、スッと頭に入ってきますよ。
6.努力義務?法的義務?:「努めなければならない」と「しなければならない」~この違い、意外と大きい!~
- 「~するよう努めなければならない」
- できる限り頑張ってね!というお願いベース。
- 「~しなければならない」
- これは絶対!守らないとダメ!という命令ベース。
得点アップの知恵:
選択肢の語尾が「~努める」なのか「~する」なのかで、〇×が変わること、結構あります。
細かいけど、見逃し厳禁!
【知っておきたい最終エール】試験直前、これだけはもう一度自分に聞いてみて!
これまで色々なコツをお伝えしてきましたが、最後に、 特に「これを意識するだけで点数が変わった!」と多くの合格者が実感した、 とっておきのチェックポイントを伝授します。
試験直前、もう一度、自分に問いかけてみてください。
- 「ただし書き」、本当に本当に読み込んでる?
- 「『ただし』って言葉を見たら、目がキラリと光るくらいじゃないと!」 そう、例外規定にこそ、合格への近道が隠されています。 読み飛ばしなんて、もったいないお化けが出ますよ!
- 過去問で「ただし書き」がどう料理されてきたか、もう一度じっくり味わってみてください。
- 用語の定義、人に説明できるくらい自分のものになってる?
- 「たぶん、こんな感じ…」じゃ、ダメなんです! 法規の言葉は、一つ一つがカチッと決まっています。
- 「特定行政庁」と「建築主事」、この二人の役割分担、パッと説明できますか?
- 一つでも曖昧な言葉があったら、それは伸びしろです!今のうちにしっかり叩き込みましょう。
- 数字のキワキワ、「未満」と「以下」の罠、見抜けてる?
- 「200m²未満ならOKだけど、200m²ちょうどはアウト!」みたいな、 意地悪な引っかけ問題、大好きですよね、試験官は(笑)。
- 具体的な数字を思い浮かべて、「これはどっちだっけ?」とシミュレーションする癖、つけてますか? その一手間が、本番であなたを救います。
- 法令集、行ったり来たりしてる?法・令・規則の連携プレーを意識!
- 建築基準法って、法律だけじゃなくて、 施行令(具体的な数字とか)、 施行規則(もっと細かいルール)と、チームで動いてるんです。
- 「この条文の詳しい話、確か令のあそこに書いてあったな…」と、頭の中でリンクを張れるようになると、もう法規マスターは目前です!
- 過去問、「解いて終わり」じゃ、あまりにもったいない!
- 過去問は、ただの〇×ゲームじゃありません!
- 「なぜこの選択肢が正解で、他はダメなのか?」
- 「出題者は、受験生のどこを試そうとしているのか?」 そこまで深掘りして初めて、過去問は最高の先生になってくれます。
- 間違えた問題は、あなたの弱点を教えてくれる宝物。 解説を読んでフムフム…じゃなくて、必ず条文に立ち返って、「そういうことか!」と膝を打つ体験を大切にしてください。
最後に…あなたの努力は、絶対に裏切らない!
法規の勉強って、地味で、終わりが見えなくて、 心が折れそうになることもありますよね。
でも、今日お伝えしたような「ちょっとしたコツ」を意識するだけで、 見える景色が少し変わってくるはずです。
大切なのは、 条文の一つ一つの言葉と、真剣に向き合うこと。 そして、それを自分の知識として、血肉に変えていくこと。
試験本番まで、やれることはまだたくさんあります。
焦らず、でも確実に、一歩一歩進んでいきましょう。
あなたが試験当日、自信を持って問題用紙を開き、 実力を最大限に発揮できることを、心から応援しています!
頑張ってください!