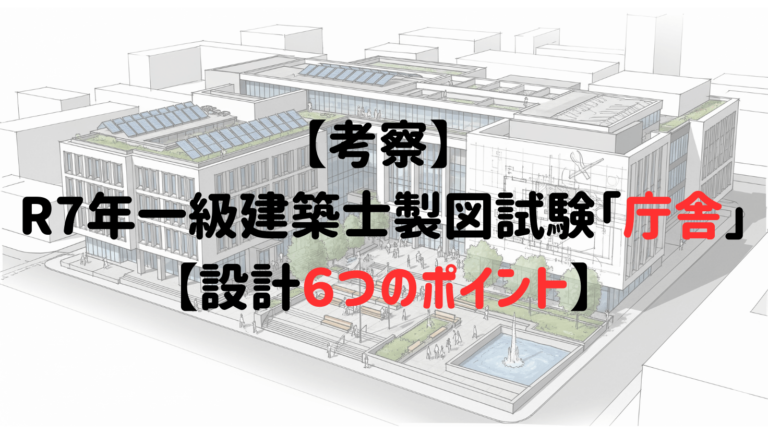こんにちは!
R7年の課題は、「庁舎」ですね。詳しくはこちら
公共建築の中でも特に多機能性が求められ、計画の腕が試されるやりがいのあるテーマです。
今回の試験課題と、これまでの経験を活かし、「庁舎設計で高得点を狙うための6つのポイント」を特別にお伝えします。
これらを意識して設計に臨めば、きっと試験官に「おっ!」と思わせる計画がまとまるはずです。
1. 市民と職員、それぞれの動線とゾーニングを明確にせよ!
庁舎は、市民が訪れ、職員が働く、二つの顔を持つ建物です。だからこそ、
- 市民動線と職員動線をいかに明快に分離するか
- 必要な箇所ではスムーズに連携させるか
が、計画の肝となります。
試験でありがちなのが、動線がごちゃ混ぜになり、利用者も職員も迷ってしまうような計画です。例えば、
- 窓口サービスは市民がアクセスしやすい低層階に集約
- プライバシーやセキュリティを確保できる執務室は高層階に配置
といった、機能に応じたフロアゾーニングを徹底しましょう。課題文にも「明快な動線計画」とありますから、ここでの減点は致命的です。
エントランスからのアプローチ、各階への動線計画を、常に利用者目線でチェックしてください。
2. ユニバーサルデザインとバリアフリーは「当たり前」に完璧に!
近年、公共建築におけるバリアフリーやユニバーサルデザインは、もはや「配慮」ではなく「必須」です。
高齢者、障がい者、ベビーカー利用者など、多様な人々が利用することを前提とした計画は、高得点を取るための最低条件。
具体的なポイントは以下の通りです。
- 段差の解消
- 適切な勾配のスロープ、手すりの設置
- 広々とした多目的トイレの配置と寸法
- 誘導ブロック
- 分かりやすいサイン計画
など、細部にわたる配慮が必要です。
単に要求されたから設けるのではなく、「誰もが使いやすいか?」という視点で、具体的な空間イメージを持って設計を進めましょう。
3. 環境性能と省エネルギーは「具体的な工夫」でアピールせよ!
省エネルギーやCO2排出量削減は、もはや公共建築の設計では外せないテーマです。
しかし、ただ「省エネに配慮しました」と書くだけでは高得点には繋がりません。
計画に盛り込むべき具体的な手法は多岐にわたります。
- 高断熱・高気密化
- 自然採光・自然換気の積極的な利用
- 庇やルーバーによる日射遮蔽
- 高効率な設備機器の採用
- 太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入
など、具体的な手法を計画に盛り込み、その効果を「計画の要点等」で明確に説明できるかがポイントです。
課題文の「省エネルギー、二酸化炭素排出量削減」にしっかり応える計画を立てましょう。
4. 構造計画は「安全性と経済性、機能性」のバランスを見極めよ!
庁舎は、大勢の人が利用し、かつ災害時には機能維持が求められる建物です。そのため、構造計画は極めて重要。
課題文にも「構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する」とあります。
特に意識すべきは以下の点です。
- 耐震性の確保:大地震時にも建物の機能が維持できるよう、適切な耐震等級や構造形式を選定する。
- 架構形式とスパン割り:要求室のゾーニングや設備シャフト、避難経路などを考慮し、効率的かつ合理的なスパン割りを計画する。
- 経済性への配慮:過剰な構造とせず、コストと安全性のバランスを考慮した部材選定を行う。
構造は、単なる力の流れだけでなく、建築計画全体の骨格となる部分です。機能性、経済性、そして安全性を総合的に考慮した計画を心がけましょう。
5. 防災・BCP(事業継続計画)は「地域の拠点」として考えよ!
庁舎は、災害時には地域の防災拠点としての役割を担います。
今回の課題にも「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする」とありますね。
単に耐震性を確保するだけでなく、災害発生後の事業継続(BCP)の視点を取り入れた計画が重要です。
- 非常用電源の確保(自家発電設備と燃料貯蔵)
- 防災備蓄スペースの確保
- 災害対策本部の設置場所
- 停電時でも機能する通信設備
など、限られた時間の中で、どこまで具体的な対策を盛り込めるか、学科Ⅰ・Ⅱの知識がモノを言います。
6. 周辺環境との調和と「地域への貢献」を忘れずに!
庁舎は、その地域のシンボルであり、顔となる建物です。
- 敷地の周辺環境に配慮し、景観に溶け込むようなデザイン
- 地域住民が利用できる公開空地や広場の設置
- 地域交流スペースの確保
などを検討することで、単なる行政施設を超えた「地域に開かれた庁舎」としての価値を高めることができます。
試験では、この「地域性」や「公共性」に対する理解度が問われることも少なくありません。
ただ要求室を配置するだけでなく、建物が地域に対してどのようなメッセージを発するのか、という視点も持ち合わせましょう。
さいごに
今はまだ不安に感じることもあるかもしれませんが、大丈夫です。
これらのポイントを頭に入れ、焦らず、しかし着実に、一つ一つの要求を丁寧に図面に落とし込んでいく練習を重ねてください。毎日の積み重ねが、必ず合格へと繋がります。
皆さんの健闘を心から応援しています!