お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は、一級建築士製図試験の「構造計算の方法」について考えてみました。
結論としては、
・3階建ての場合
「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOK!(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)・5階建ての場合
①高さが20mを超える場合は、許容応力度等計算をすればOK!(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
②高さが20m以下の場合は、「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算。)・7階建ての場合
許容応力度等計算をすればOK!(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
です。
では、解説していきますね!
「構造計算の方法」を調べる
 「構造計算の方法」を調べるときは、法20条→令81条を順番に見ていきます。
「構造計算の方法」を調べるときは、法20条→令81条を順番に見ていきます。
これらをざっくりまとめると、このように↓なります。
| 法20条 | 令81条 | 構造計算の方法 |
| 一号 | 1項 | 時刻歴応答解析 |
| 二号 | 2項一号 | 保有水平耐力計算、限界耐力計算 |
| 2項二号 | 許容応力度等計算 | |
| 三号 | 3項 | 許容応力度計算+屋根ふき材の検討 |
| 四号 | 4項 | 構造計算不要 |
| ※上位の「構造計算の方法」にもできる。 | ||
ちなみに、法20条一号~四号分け方については、こちら↓をどうぞ。
過去問を見てみましょう

| 年 | 課題名 | 階数 | 面積 |
| 令和2年 | 高齢者施設 | 地上3階 | 2400㎡~3000㎡ |
| 令和元年(10月13日) | 美術館の分館 | 地上3階 | 2000㎡~2400㎡ |
| 令和元年(12月8日) | 1800㎡~2200㎡ | ||
| 平成30年 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | 地上3階 | 2300㎡~2800㎡ |
| 平成29年 | 小規模なリゾートホテル | 地下1階地上2階 | 2400㎡~2800㎡ |
| 平成28年 | 子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) | 地上3階 | 2000㎡~2500㎡ |
| 平成27年 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅(基礎免振構造を採用した建築物である。) | 地上5階建 | 2600㎡~3100㎡ |
| 平成26年 | 温浴施設のある「道の駅」 | 地上2階 | 1800㎡~2200㎡ |
| 平成25年 | 大学のセミナーハウス | 地上2階 | 1500㎡~1800㎡ |
| 平成24年 | 地域図書館(段床形式の小ホールのある施設である。) | 地下1階地上2階 | 1800㎡~2200㎡ |
| 平成23年 | 介護宋人保険施設(通所リハビリテーションのある地上5階建ての施設である。) | 地上5階 | 3400㎡~4000㎡ |
| 平成22年 | 小都市に建つ美術館 | 地上2階 | 1800㎡~2200㎡ |
| 平成21年 | 貸事務所ビル(1階に展示用の貸スペース、基準階に一般事務用の貸スペースを計画する。) | 地下1階地上7階 | 5200㎡~5800㎡ |
| 平成20年 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなら複合施設 | 地下1階地上7階 | 6000㎡ |
| 平成19年 | 子育て支援施設のあるコミュニティーセンター | 地上3階 | 2000㎡~2500㎡ |
| 平成18年 | 市街地に建つ診療所等のある集合施設(地下1階、地上5階建) | 地下1階地上5階
|
3000㎡~3600㎡ |
| 平成17年 | 防災学習のできるコミュニティ施設 | 地上2階 | 1800㎡~2300㎡ |
| 平成16年 | 宿泊機能のある「ものづくり」体験施設 | 地上3階 | 2200㎡~2600㎡ |
| 平成15年 | 保育所のある複合施設 | 地下1階地上3階 | 2200㎡~2700㎡ |
つまり、ざっくり言って、この↓3パターンが多いです。
・地上3階建て
・地上5階建て
・地上7階建て
では、この3パターンについて、「構造計算の方法」はどれにしたらいいか考えてみます。
(ちなみに、構造は鉄筋コンクリート造とします。)
地上3階建て
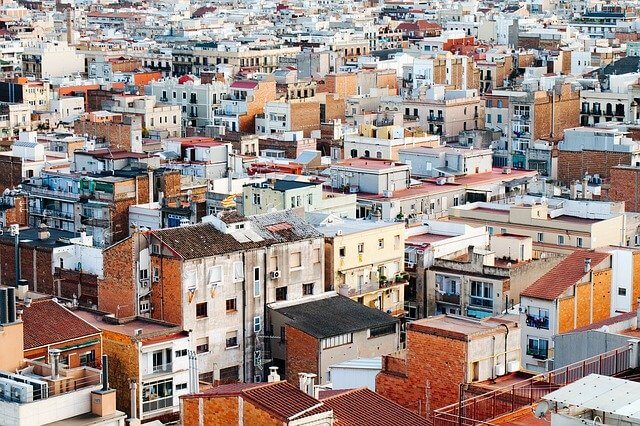
地上3階建ての場合、階高を3m~4mとすると、この建築物の最高高さは、約10m~13mです。
では、
・地上3階建て
・鉄筋コンクリート造
・高さ10m~13m
の場合、どの構造計算を採用したらいいでしょう?
答えは、「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
理由は、法20条第三号に該当するからです。
ということで、
地上5階建て

地上5階建ての場合、階高を3m~4mとすると、この建築物の最高高さは、約16m~21mです。
では、
・地上5階建て
・鉄筋コンクリート造
・高さ16m~21m
の場合、どの構造計算を採用したらいいでしょう?
答えは、2パターンあります。
①高さが20mを超える場合は、許容応力度等計算をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
②高さが20m以下の場合は、「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
理由は、
①の場合は、法20条第二号
②の場合は、法20条第三号
に該当するからです。
ということで、
①高さが20mを超える場合は、許容応力度等計算をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
②高さが20m以下の場合は、「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算。)
地上7階建て

地上7階建ての場合、階高を3m~4mとすると、この建築物の最高高さは、約22m~29mです。
では、
・地上7階建て
・鉄筋コンクリート造
・高さ22m~29m
の場合、どの構造計算を採用したらいいでしょう?
答えは、許容応力度等計算をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
理由は、法20条第二号に該当するからです。
ということで、
さいごに

以上、【一級製図】「構造計算の方法」はどれにしたらいいの?についてでした。
結論は、
・3階建ての場合
「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOK!(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)・5階建ての場合
①高さが20mを超える場合は、許容応力度等計算をすればOK!(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
②高さが20m以下の場合は、「許容応力度計算+屋根ふき材の検討」をすればOKです。(もちろん、これよりも上位の構造計算。)・7階建ての場合
許容応力度等計算をすればOK!(もちろん、これよりも上位の構造計算もOKです。)
です。
製図試験では、法令集を見ることができないので、このことは覚えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございまし。
他の記事も読んでみてくださいね!
