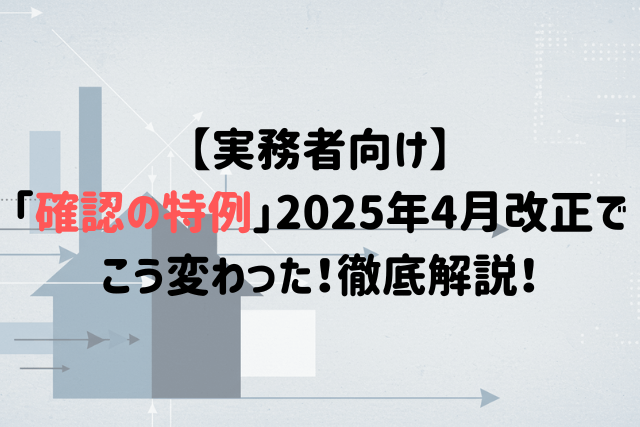こんにちは!
2025年4月から建築基準法が改正され、特に「4号特例」の扱いが大きく変わりました。 これは、建築実務に携わる私たちにとって、避けて通れない重要な変更点です。
日々の業務に直結するポイントをしっかり押さえていきましょう。
そもそも「4号特例」って何だった? なぜ今、見直し?
ご存知の通り、「4号特例」とは、建築士が設計する比較的小規模な建築物(いわゆる4号建築物)について、建築確認申請時の構造関係規定などの審査が一部省略される制度でした。 手続きの迅速化に役立ってきましたね。
今回の改正の背景には、
- 建築物の省エネ性能の向上義務化
- 構造安全性のさらなる確保
といった社会的な要請があります。 これに対応するため、従来の特例範囲が見直されることになりました。
▼ 最重要ポイント! 特例範囲が大幅に縮小されました ▼
2025年4月1日以降、この「4号特例」の対象となる建築物の範囲が大幅に縮小されました。
これまで特例の恩恵を受けていた多くの建物が対象外となり、確認申請の手続きや審査内容に具体的な変更が生じています。 ここは特に注意が必要です。
具体的に何がどう変わったのか?
改正前(~2025年3月31日まで)
木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下などの「4号建築物」で、建築士が設計したものは、構造関係規定などの審査が省略されていました。
改正後(2025年4月1日~)
審査省略の特例が継続されるのは、主に以下の条件を満たす小規模な建築物、いわゆる「新3号建築物」に限られます。
- 平家建てかつ 延べ面積200㎡以下
これにより、これまで4号特例の対象だった
- 多くの木造2階建て住宅
- 平家建てでも延べ面積が200㎡を超える木造建築物
は、原則としてこの特例の対象外となり、「新2号建築物」として扱われることになりました。
実務への具体的な影響は?
- 審査の実施(厳格化)
- これまで省略されていた構造関係規定
- (例:壁量計算、四分割法、偏心率、N値計算による金物選定、基礎の仕様など)
- 本格施行された省エネ基準への適合 について、確認申請時に審査が行われるようになります。
- これまで省略されていた構造関係規定
- 提出図書の増加
- 上記の審査に対応するため、
- 構造計算書(仕様規定の計算を含む)
- 各種伏図、詳細図
- 省エネ計算書(外皮計算、一次エネルギー消費量計算書など) といった図書の提出が新たに必要、または内容の充実が求められます。
- 上記の審査に対応するため、
- 審査期間の長期化の可能性
- 審査項目が増えるため、確認済証交付までの期間が、改正前よりも長くなるケースが想定されます。
- 特定行政庁や検査機関によっては、標準処理期間の見直しが行われている場合もありますので、事前に確認が必要です。
「新2号建築物」となる場合の主な注意点
構造関係
- 仕様規定の適合確認が必須: 壁量計算、柱の小径、横架材の断面、接合部の仕様(N値計算等に基づく金物選定)、基礎の設計など、建築基準法施行令の仕様規定への適合性を図面や計算書で明確に示す必要があります。
- 構造計算書の要否判断: 必ずしも全ての新2号建築物で許容応力度計算(ルート1)以上の詳細な構造計算が必要となるわけではありません。 しかし、
- 建物の規模、形状、立地条件(積雪、風圧など)
- または仕様規定で対応できない設計の場合 は、別途構造計算が必要となるケースが増えます。
- 2025年4月施行の新基準への対応: 小規模木造建築物の壁量基準や柱の小径基準なども見直されています。 これらの新しい基準に適合しているかしっかりとチェックし、図書に反映させることが求められます。
省エネ関係
- 省エネ基準への適合義務化: 原則として全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられました。
- 省エネ性能に関する図書の提出と審査: 確認申請時に、外皮計算書、一次エネルギー消費量計算書などを提出し、その審査を受けることが必須となります。
💡 設計者・工事監理者として、どう対応すべきか?
- 責任の重さを再認識: 特例が縮小され審査項目が増えたからといって、設計者や工事監理者の法的責任が軽減されるわけではありません。 むしろ、基準への適合性をより明確に示す必要があり、その責任は一層重くなったと認識すべきです。
- 最新知識の習得と情報収集の徹底:
- 改正法の正確な理解はもちろん、関連政省令、告示、Q&A、各種技術基準の解説などを継続的に学習する必要があります。
- 国土交通省や建築行政情報センター、関連団体が発信する最新情報を常にチェックしましょう。
- 講習会やセミナーへの積極的な参加も有効です。
- 設計・申請プロセスの見直し:
- 初期段階での構造計画、省エネ計画の重要性が増します。
- 必要な図書作成のための時間、人員体制を確保しましょう。
- CADソフトや各種計算ソフトも改正対応版へのアップデート、または新規導入を検討する必要があるかもしれません。
- 関係各所との連携強化:
- 不明な点や判断に迷う場合は、設計の初期段階から所管の特定行政庁や指定確認検査機関に事前相談・確認を行うことが、手戻りを防ぐ上で非常に重要です。
- プレカット業者や協力事務所との情報共有、連携も密に行いましょう。
- 社内体制の整備:
- 改正内容に関する社内勉強会の実施や、チェック体制の強化も検討しましょう。
まとめ:法改正を乗りこなし、信頼される建築物を目指して
今回の建築基準法改正、特に「4号特例」の縮小は、私たち建築実務者にとって大きな変化であり、対応すべき課題も少なくありません。 手続きが煩雑になったり、設計に必要な時間が増えたりする側面は否定できません。
しかし、この改正の根底にあるのは、
- 建築物の安全性確保と質の向上
- そして省エネルギー化の推進
という、社会からの強い要請です。 私たち建築のプロフェッショナルは、この変化を的確に捉え、より一層の知識と技術の向上に努め、設計・工事監理の品質を高めていく必要があります。
常に最新情報をキャッチアップし、丁寧な設計と確実な工事監理を実践することで、社会からの信頼に応え、より安全で快適な建築物を創り出していきましょう。
この記事が、皆さんの実務の一助となれば幸いです。