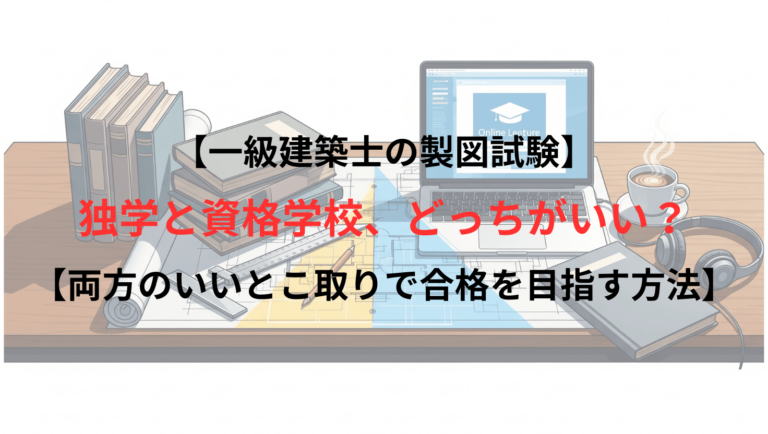一級建築士の製図試験の勉強を始めるとき、多くの人が「資格学校に通うべきか、独学で頑張るか」で悩むと思います。
資格学校は、しっかりした授業の進め方や、一緒に頑張る仲間がいるのが心強いですよね。でも、お金も時間もかなりかかります。
一方で独学は、自分のペースでできるし、お金もあまりかかりません。
でも、自分の図面がいいのか悪いのか客観的に見てもらえないし、一人で勉強していると孤独を感じやすいのがつらいところです。
でも、実は「どっちか一つ」を選ぶ必要はないのかもしれません。
合格への近道は、それぞれの良いところをうまく利用して、足りない部分を補い合う「ハイブリッドな勉強法」にあると、私は考えています。
この記事では、「資格学校に通っている人」と「独学で頑張っている人」、それぞれの状況に合わせて、すぐに試せる「いいとこ取り」のやり方を紹介します。
資格学校に通っている人へ:「授業についていくだけ」から一歩進むための工夫
資格学校に通っていると、質の高い教材や情報が手に入るので安心感がありますよね。でも、その環境に慣れすぎて、「毎週の課題をとにかく終わらせる」だけになっていませんか?それだと、周りの人と差がつきにくいかもしれません。
学校という土台をうまく使いながら、自分一人で深く考える時間もプラスして、周りから一歩リードしましょう。
1. 自分だけの「練習テーマ」を決めてみよう
学校の課題をやるとき、ただ「良い評価をもらう」ことだけを目標にしていませんか?もったいないです。そこに、自分だけの「今週のテーマ」を付け加えてみましょう。
例えば、こんな感じです。
- 「今週は、エスキスにかかる時間を15分短くするのを目標にしよう」
- 「今回は、苦手な階段まわりの図面を誰よりも詳しく描いてみるぞ」
- 「線の種類を3つ、きれいに使い分ける練習に集中する」
こんな風に、いつもの課題を「自分の苦手分野を克服するチャンス」と考えると、勉強の質がぐっと上がります。
全体をなんとなく良くしようと思うより、一つのことに集中するほうが、結果的に全体のレベルアップにつながります。
2. 「なんで間違えたんだろう?」と、じっくり振り返る時間をつくる
授業で先生から図面の間違いを教えてもらった後、「そっか、次から気をつけよう」だけで終わらせていませんか?それだけだと、たぶんまた同じミスをしてしまいます。
本当に大事なのは、その後の独りの時間です。なぜそのミスをしたのか、自分の考え方のどこに問題があったのか、誰にも邪魔されずにじっくり考えて、メモに残しておくのがおすすめです。
- 考え方のクセ: 「自分はいつも、建物の北側から光を取り入れるのをすぐ諦めちゃうな…」
- 知識不足: 「そもそも、この建物の構造でどれくらいの柱の間隔が必要か、よく分かってなかったな」
- 時間配分のミス: 「計画に時間を使いすぎて、図面を描くときに焦ってしまったのが原因だ」
この「じっくり振り返る時間」こそ、学校の速いペースの中ではなかなか取れない、独学の強みなんです。
独学で頑張っている人へ:孤独から抜け出し、客観的な意見をもらう工夫
独学の良さは、自分のペースで、自分の苦手なことだけに時間を集中できる点です。
でも、一番の課題は「自分の図面がいいのか悪いのか、自分だけでは分からなくなること」と「孤独」ですよね。間違ったやり方でずっと努力してしまうのは、一番避けたいところです。
そこで、独学を続けながら、学校に通うメリットである「他の人との関わり」を外から取り入れてみましょう。
1. SNSを「無料の意見交換会」として使ってみる
今の時代、X(旧Twitter)やInstagramは独学の強い味方です。ただ情報を見るだけでなく、自分から発信してみましょう。
#一級建築士製図試験 のようなハッシュタグをつけて、自分のエスキースや図面を「えいっ」と投稿してみるのがおすすめです。そのとき、「この動線計画について、ご意見もらえると嬉しいです」「矩計図のこの部分に自信がないのですが、アドバイスお願いします」のように、具体的にどこを見てほしいか書くのがコツです。
そうすると、全国の受験生仲間や、ときには合格した先輩から、自分では思いつかないような意見がもらえることがあります。SNSを、自分だけの教室みたいに活用しましょう。
2. 「単発の添削サービス」をうまく利用する
SNSだけだと、どうしても断片的なアドバイスになりがちです。そこで頼りになるのが、個人の先生がやっている「単発の添削サービス」です。
- 勉強の初めごろ: 自分の今の実力と、今後の勉強の方向性を教えてもらうために
- 勉強の半ばごろ: 自分のプランのクセや弱点を、プロの視点から見てもらうために
- 試験の直前期: 合格レベルに届いているか、最後のチェックをしてもらうために
このように、大事な節目でプロに見てもらうと、勉強の方向を間違えずに進めます。一年分の授業料は高くても、数万円の添削サービスは合格のための「自己投資」だと考えてみてはどうでしょうか。
3. 「オンライン勉強会」で仲間と話す
今はオンラインで気軽に人と繋がれます。「製図試験の勉強会」をSNSなどで探してみるのも良いですし、なければ自分で「週に一回、エスキース見せ合いませんか?」と呼びかけてみるのもアリです。
数人で集まってお互いの図面を見るだけでも、「へぇ、他の人はこう考えるんだ!」という発見がたくさんあります。締め切りもできるので、独学の敵である「サボりたくなる気持ち」に打ち勝つきっかけにもなります。
まとめ:最後は、自分に合ったやり方を見つけるのが一番
一級建築士製図試験の勉強に、「これさえやればOK」という絶対の正解はありません。
資格学校に通っていても、自分で考えて勉強する姿勢がなければ伸び悩みます。 独学で頑張っていても、他の人の意見を聞かなければ、独りよがりになってしまうかもしれません。
大事なのは、今の自分の環境を活かしつつ、足りない部分をうまく外から取り入れていくことです。
資格学校に通うあなたも、独学で頑張るあなたも、明日からこの「ハイブリッドな勉強法」を試してみませんか?その小さな工夫が、合格をぐっと引き寄せる一歩になるはずです。
応援しています!