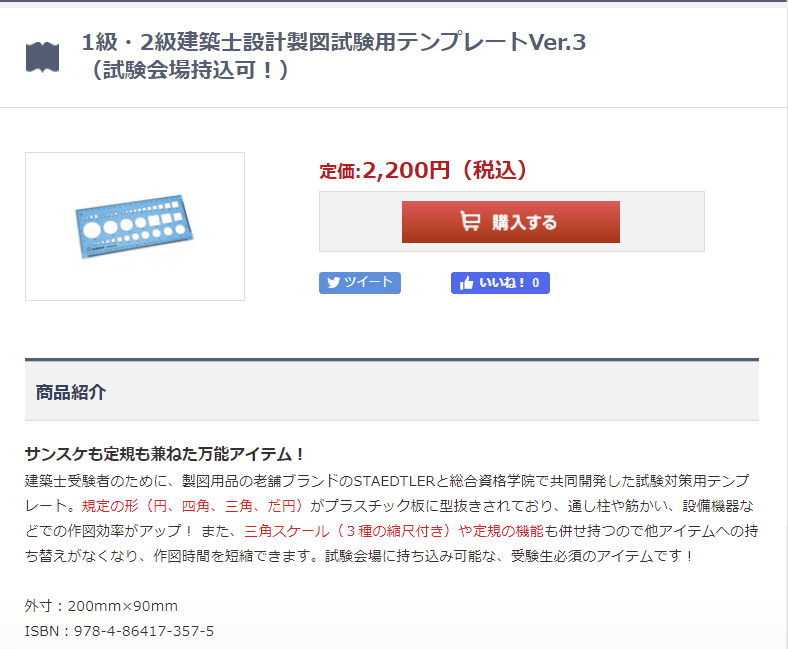お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
学科試験終わりましたね~。次はいよいよ製図試験ですね~。
ちなみに僕は、製図試験を4回受けました。
詳しくは、こちら↓をどうぞ。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログをお読みいただきありがとうございます。 令和2年度の一級建築士学科試験が終わりましたね。お疲れさまでした。あっという間でしたね。 […]
4年間も勉強したので、数えきれないくらいの道具を試してみました。
今回は、そんな僕が厳選する製図道具を紹介していきます。

そこだけでも読んでもOK!
製図版
ムトーの製図版です。
新宿の世界堂で購入しました。
ぶっちゃけ、他のに比べると高めです。
でも、道具の時点で勝ってる!と思いたかったのでこれにしました。(笑)
これのいいところは
・製図版の角度を二段階に変えることができる
・カバーがかっこいい
ところです。
この角度を二段階で変えることができるのは、他にはないはず。
作図の練習してて、自分にあう角度に合わせることができるのです。
自分に合う角度が分かると、合格に近づいた気になれますよ!

テンプレート
総合資格のテンプレートです。
(出典:総合資格出版サイトより)
これは、アマゾンとかでは買えません。
総合資格出版サイト↓より購入可能です。
https://www.shikaku-books.jp/shopbrand/ct8/
これのいいところは、
・厚みがあるので動かしやすい。
・平行定規の上を滑らしやすい
です。
総合資格に通っている人の9割は、これを使っていると思います。
これ以上のテンプレートはありません。

蛍光ペン
フリクションの蛍光ペンです。
これのいいところは、やっぱり、消せるところです。
問題文を一生懸命読んでいると、線の色って、間違えがちです。
そんなとき、普通の蛍光ペンなら取返しがつきません。
ただ線を引き間違っただけなのに、ぼくのように心配症な人なら、もうその時点で気分が滅入ってしまいます。
そうならないように、取返しが付くようにフリクションを使うようにしました。
そうすると、「間違っても、直せばいいじゃん!」という気持ちになり、安心感が出るのです。
心配性なあなたは、絶対フリクションのマーカーを使ったほうが、安心できますよ!

明るい色のフリクション
ペンもマーカーに同様に消せることが大事です。
また、
「明るい色」を使うことがミソです。
具体的には、次の2本です。
ピンクのフリクション
ライトブルーのフリクション
このフリクションには、赤と青もあります。
しかし、
ぼくのおすすめは、ピンクとライロブルーです。
理由は、
ピンクとライロブルー、つまり、明るい色で線や書き込みをした方が、文字が浮かびあがってきて、目に入りやすくなるからです。
大事な条件を見落としにくくなるからです。
ぶっちゃけ、このフリクションの赤と青は、結構暗めです。
「線を引いて明るくなった問題文」と「線を引いて暗くなった問題文」
あなたならどっちの方が、気持ちが上がりますか?
もちろん、明るくなった問題文ですよね?
人間の気持ちは、目で見たもの、つまり、視覚によってガラッと変わってきます。
そうであるならは、自分の気持ちをアップされるためにも、明るい色を用いた方が絶対いいのです。

スケール
これは、長いもの、つまり、30cmのものを準備しましょう!
理由は、
寸法をチェックしやすいからです。
たとえば、長辺方向の合計スパンがあっているか確認するときを考えてみましょう。
30cmのスケールであれば、一発でチェックすることができます。
しかし、15cmであれば、短いので一発でチェックすることができません。
この差はデカいです。時間のロスだけでなく、間違えるリスクも伴います。
あなたなら、どっちがいいですか?
そうですよね。
時間も短縮でき、間違えるリスクを減らせるほうを選びますよね。
ちょっと値段はしますが、必ず30cmのスケールをそろえましょう!

シャーペン
シャーペンは、どれなら図面や要点がキレイに書けるか。本当に何本何本も試しました。高いのから安いのまで。
そんな僕がおすすめするのが、この2本です。
製図用はこれ↓
ぺんてるの0.5mmです。
これのいいところは、上は軽くて、下が重くなっているところです。
つまり、
軽量化されているだけでなく、下に重心があるので
動かしやすいだけでなく、線に力が伝わりやすいのです。
要点は書くときは、絶対これ!
クルトガの0.5mm。
クルトガって知ってますよね?
芯が回転しながら出てくるので、文字の太さが均一になるのです。
要点を書くときこれと使うことによって、全然印象が違います。
文字の太さが均一なので、めちゃくちゃキレイに見えるのです。

三角定規
ステッドラーの三角定規30cm。
このサイズであれば、大きすぎず、小さすぎず、使い勝手がいいです。どんな場面でもこれだけで済みます。
それに、厚みもあり、動かしやすいです。

その他
電卓
自分の好きなものを揃えましょう!
ただし、[M +]と[M−]が使えるものにしましょう!
この[M+]と[M-]を使えるようになると、マジで面積計算などが楽になります。
ググればやり方が出てくるので、必ずマスターしましょう!
消しゴム
ペンタイプなので、ペンと同じように使えます。
握り替えるときに、違和感がありません。
また、これ一本あれば、大きい間違い・小さな間違いなんでも消せます。
刷毛
これは、なんでもOKです。
ちなみに、ぼくは4回目にして刷毛を使い始めました。(笑)
それまでは、口でふーっとして消しゴムのカスと飛ばしていました。
だって、こっちの方が時間ロスしないじゃんって思ってたからです。
でもそのせいで、図面は黒くて汚かったです。
やはり見た目は大事です。
キレイにするために、刷毛は必須です。
【重要】さいごに
以上、【厳選】製図4回目にした受かった僕がおすすめする製図道具とは?でした。
さいごに一番伝えたいなことがあります。
それは
ぼくが製図4回目を受けたときは、上記で紹介したもの以外は、机の上に置きませんでした。
理由は、余計なものがあると、無駄な動きをしたり、気が散ってしまうからです。
そしたら合格できました。
「LESS IS MORE」
ミースファンデルローエの言葉です。
「少ないことは、豊かなこと」
つまり、今回の道具について言うと
「少ないほうが、キレイな図面がかける」ってことです。
要は、道具は、必要最低限あればいいのです。
その方が、キレイな図面がかけるのです。
練習ではいろいろ試すのはいいですが、最終的に試験を受けるときは、道具は少なくした方がいいのです。身軽になった方がいいのです。
これが道具に対する大事な「考え方」なのです。
是非、あなたもこの「考え方」を取り入れてくださいね!
必ずやいい方向に進んでいくでしょう。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね。