お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
一級建築士製図試験で用いる面積区画は、
・1500㎡?
・1000㎡?
・500㎡?
どれを使うでしょうか?
答えは、1500㎡以内ごとの区画です。
では、なぜ1500㎡以内ごとの区画を使うのでしょうか?きちんと理由は分かっていますか?
ということで、今回は
【一級製図】面積区画は、1500㎡以内ごとの区画を用いる理由について解説していきます。
先に結論を言うと
問題文に「耐火建築物」とする。と書いてあるから。
(※令和2年問題文参照 https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-2nd-mondai.pdf)
です。
では、サクッと解説していきます。

【根拠】 令112条(防火区画)第1項
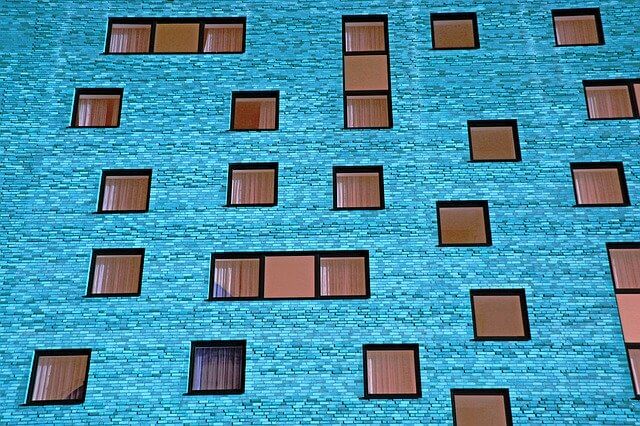
主要構造部を耐火構造とした建築物、法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500㎡を超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)1500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りではない。
一 (省略)
二 (省略)
解説
条文の出だしに、この条文の対象となる建築物が4つ書いてあります。
①主要構造部を耐火構造とした建築物
②法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物
③第136条の2第一号ロ
④第二号ロ
つまり、
この4つの建築物のいずれかに該当し、床面積の合計が1500㎡を超えたら、
1500㎡以内ごとに区画しなければならないのです。
製図試験では、どういう建築物にするでしょうか?
よって、
①主要構造部を耐火構造とした建築物に該当するので、
1500㎡以内ごとに区画しなければならないのです。
ちなみに、
・4項の500㎡以内ごとの区画
・5項の1000㎡以内ことの区画
の対象となるのは、原則、準耐火建築物の場合です。
詳しくは、こちら↓をどうぞ!
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。ブックマークお願いします。 令112条第4項と第5項の違いについてです。 つまり、「500㎡」と「1000㎡」の区画の違いについて解説していきます。 […]
よってまとめると
問題文に「耐火建築物」とすると書いてあるので、
500㎡や1000㎡区画ではなく、1500㎡区画に該当するのです。
さいごに

以上、【一級製図】面積区画は1500㎡以内ごとの区画を用いる理由 についてでした。
結論は、
問題文に、「耐火建築物」とする。と書いてあるから。
(※令和2年問題文参照https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-2nd-mondai.pdf)
です。
せっかくつらい思いをして勉強するのであれば、こういう根拠も併せて習得しちゃいましょう!
必ずや役に立つときがきます。
「人生無駄なし」です。
さいごまでお読みいただきありがとうごさいました。
他の記事も読んでみてくださいね。

